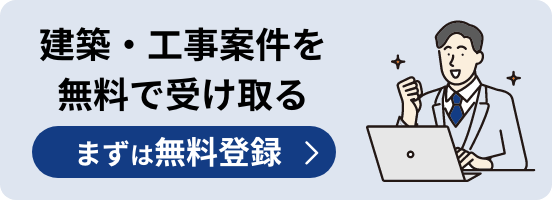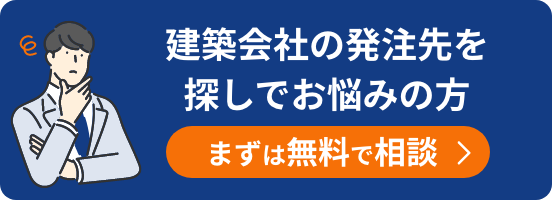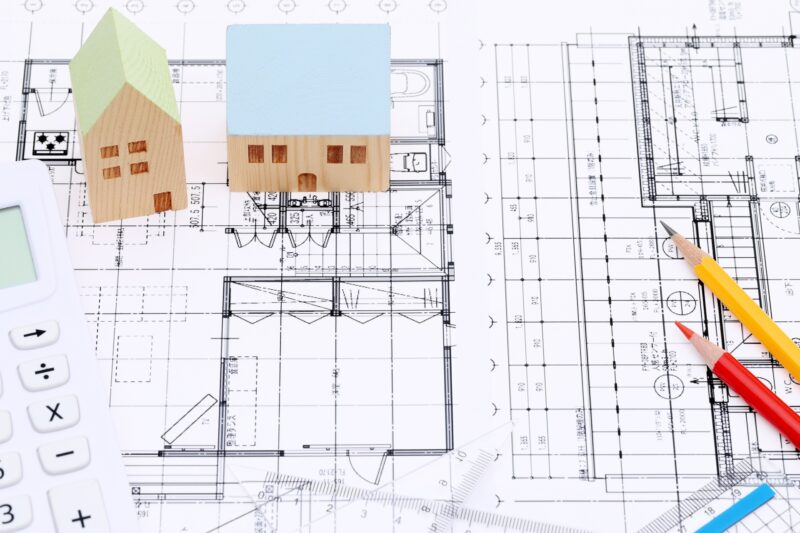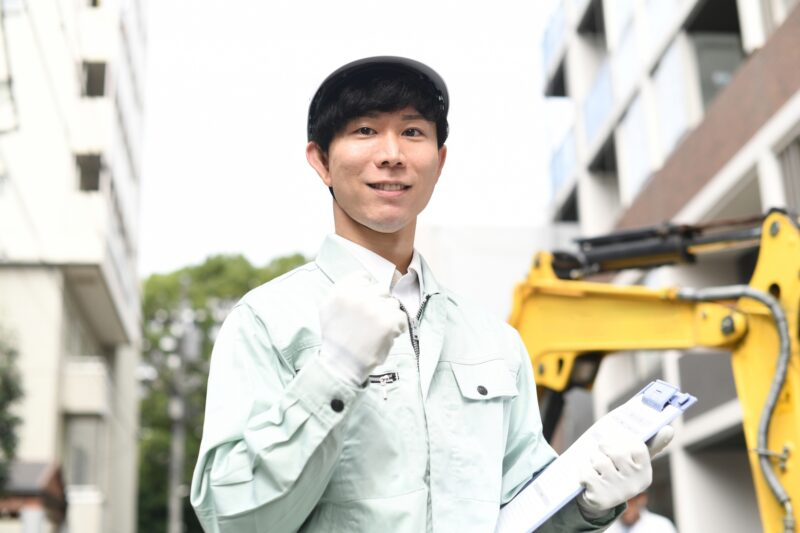建築工事を希望の予算内に収めるためには、設計の各フェーズにおいて適切なタイミングで概算見積(概算積算)を行い、予算(目標コスト)との整合性をはかるよう設計内容をコントロールすることが重要です。この記事では概算見積の目的や設計情報と概算手法の関係について、設計段階ごとに解説するとともに、発注者からみた概算見積の信頼性と有効活用についても説明します。
概算見積(概算積算)とは?
建築工事の概算見積(概算積算)とは、実施設計が完了する前の川上段階で、限られた設計情報(インプット情報)から概略の工事金額(アウトプット情報)を算定するものです。
設計が進むにつれ、建物情報(粒度)は多くなり、確定する内容(確度)も多くなっていきます。したがって、積算対象項目が増えるとともに仕様なども明確になることから、算定結果(概算工事費)の精度も高まっていくことになります。
概算見積の目的
【発注者側】
概算見積によりコストを算定する主体のひとつは、通常、発注者側に立つ設計者(設計事務所)あるいはCMR(コンストラクション・マネジャー)などの専門家です。
発注者の予算(目標コスト)を有効に使って、価値の高い(発注者のニーズを満足する)建物を設計するには、設計の進捗に応じて概算見積をおこない、予算と設計内容を整合させていくことが重要です。概算工事費が予算を超過した場合は、VE(バリュー・エンジニアリング)などにより設計内容の変更をおこないますが、当然発注者との協議が欠かせません。
建築プロジェクトにおいては、予算を上回る設計をしてしまうケースが多くみられます。また、建設物価の変動が激しい時期においては、このような市況の変化についても必要なタイミングで確認していく必要があります。
もし基本設計までに概算見積をおこなわず、実施設計完了後に詳細な積算(精算積算)をおこなった場合は、工事費が予算を大幅にオーバーする可能性が高く、設計内容の修正に膨大な手間と時間を要することになり、プロジェクトそのものが頓挫しかねません。そのため、事業構想段階および設計の各段階(企画設計、基本計画、基本設計など)において適切に概算積算をおこない、設計内容と予算とを整合させながら設計を進めることが重要となるのです。このような活動は、「コスト管理(コストマネジメント)」のうち「コストコントロール」と呼ばれています。
【受注者側】
概算見積によりコストを算定する主体の二つ目は、受注者側である総合建設会社(ゼネコン)や専門工事会社(設備サブコンなど)といった施工者です。施工者における概算見積は、工事受注を目的としていますが、以下のように三つの局面があります。
(1)設計施工
「設計施工」の場合は、前述した発注者側と同様に、設計段階において「コストコントロール」のために概算見積をおこないます。受注者側における概算見積は、事前原価(NETなどと呼ばれる)としての工事金額を算定し、発注者の予算を推測しながら目標コスト(この場合は目標NET)との整合性を確認し、適正な利益を確保することが目的です。自社設計部門と連携して設計の進捗に応じて概算工事費(NET)を算定し、必要に応じて概算見積書を作成し発注者へ提出します。概算工事費が目標コストを超過した場合は、VE(バリュー・エンジニアリング)などにより設計内容の変更をおこないますが、適時変更内容を発注者に説明して了解を得ることも重要です。
また、受注者側には発注者の予算がはっきりと知らされていないことも多く、提出した概算見積書による発注者の反応あるいは交渉で予算を推測するケースも多くみられます。
発注者予算を把握しないままに設計を進め、実施設計完了後にはじめて発注者に工事費見積書を提出したような場合は、見積金額が予算と大きく乖離する可能性が高くなります。また、設計途中で予算をオーバーしたと推測し、発注者の了解を得ないままに発注者ニーズと異なるコストダウン設計をおこなった場合は、実施設計完了後にトラブルとなることが懸念されます。そのため、発注者に対して適切なタイミングで概算見積書を提出し、工事金額や設計内容などの確認や調整をおこなうことが、発注者にとっても施工者にとっても重要になるのです。
(2)特命発注
発注者が委託した設計事務所が設計をおこなうものの工事を担当する施工者が事前に確定している「特命発注」においても、設計の初期段階から設計者とのコミュニケーションを図り、適切なタイミングで概算見積を行うことが重要です。コストコントロールの内容は、前述した設計施工の場合と同様です。
また、この場合は、設計者が概算見積書の内容を確認することになります。施工者が提案して設計内容を変更する場合は、当然設計者および発注者との協議が欠かせません。
(3)一般のプロジェクト
設計施工や特命発注ではない一般のプロジェクトにおいては、実施設計が完了する前に施工者が発注者に概算見積書を提出するケースがあります。早期に受注者(施工者)を決めることにより、施工者の技術的なノウハウを設計に反映させたり、設計段階から資機材発注を準備し早期着工を目指すなど、コストや工期の縮減を図る目的でおこなわれます。
(4)公共工事における多様な発注方式
公共工事において、設計施工者や技術協力者を選定するために、基本設計段階などで技術提案とともに概算見積書の提出を求める場合があります。
「ECI(Early Contractor Involvement)」は、設計段階において施工ノウハウを生かした提案をおこなう「技術協力者」を求める発注方式です。提案型の総合評価落札方式で技術協力者が決定され、目標コストをクリアーすれば優先的に施工を受注できるため、民間の特命発注に近い仕組みと考えられます。
「設計施工一括発注方式(デザインビルド)」もECIと同様に提案型のプロポーザル方式で設計施工者が決定します。これらの発注方式において多くの場合は、技術提案とともに発注者が最も重視するコストに関する提案(概算見積やVE提案)が求められます。
(5)分譲マンション
マンション・デベロッパーが土地を購入する段階で、ゼネコンから概算見積書を徴集し、施工者および発注金額を確定させるケースもあります。この場合は、数枚の設計図(配置図、平面図など)で金額が決定されてしまうため、図面情報は少ないものの、デベロッパーの標準仕様書や過去の施工実績などを活用し、かなり詳細な概算をおこなうことが一般的です。設計完了までの間、発注者と施工者間で設計内容と工事金額についての交渉が続けられ、最終請負金額が決定されることになります。
※ これら発注者の要請に応じて提出する概算見積書は、発注者にとっては工事発注のベースとなる金額として認識されるのですが、当然一定の誤差(粒度や確度)を含んだ数字であることから、施工者側にとってはリスクの高いものとなります。建設物価の変動が激しい状況でもあり、提出される金額や工事費内訳明細書に記載される内容、あるいは発注者・施工者双方のリスクなど、概算見積書の扱いには十分な注意が必要です。
※ VE(バリュー・エンジニアリング):製品やサービスの「価値」をそれが果たすべき「機能」と、そのためにかける「コスト」との関係で把握し、システム化された手順によって「価値」の向上をはかる手法。
価値(バリュー)=機能/コスト
設計段階における設計情報(インプット)とコスト(アウトプット)
建築プロジェクトと設計
建築プロジェクトにおいては、事業構想の段階でフィジビリティスタディ(実現可能性調査)をおこない、事業の立ち上げが決定されます。事業の核となる建物の設計は、発注者のニーズを満足するとともに、事業予算内で完成するようコントロールされる必要があります。
企画設計は、法的な条件や敷地条件などから、発注者のニーズを踏まえて「どのような建物にするか」といったアウトラインを定める段階です。
基本計画段階は、建物のおおよその内容が検討され、建物の基本仕様が固まる最も重要な段階です。
基本設計段階は、建物の基本的な内容がほぼ決定し、実施設計へと進んでいく段階です。国土交通省告示第8号で成果品が定められています。
実施設計段階は、確認申請用の設計図書と工事発注・施工用の設計図書を完成させる段階です。この段階では、詳細な積算(精算積算)がおこなわれます。
概算見積手法と基本的な考え方
概算見積には様々な呼び名と手法が使用されています。
例えば、設計初期段階であれば精度が低いという意味合いで「超概算・大概算・粗概算」など、また設計が進んでくれば「精概算」などと呼んでいる例もみられます。概算手法をあらわす呼び名としては、設計初期段階の「床面積法(坪単価など)」「ユニット法(病院1ベッド当り等)」あるいは数量と単価で構成された「積上げ概算法」など様々です。「A概算」「B概算」などアルファベットで概算レベルをあらわすこともあります。いずれにしても、概算手法は体系化されることが重要で、感覚的な概算名称はあまり意味をなしません。
概算見積(概算積算)は、「設計内容(インプットされる設計情報)」をある方法で処理し「概算工事費(コスト情報)としてアウトプットする」活動です。したがって、インプットする設計情報(粒度と確度)によって処理する方法(概算手法)が異なり、アウトプットされるコスト情報(粒度と確度)も定まってきます。以上のことから、設計段階ごとにインプットする設計情報とアウトプットされるコスト情報およびそのための概算手法の関係について、具体的に整理しておくことが重要となるのです。
面積当たり単価で概算工事費を算定する方法いわゆる「坪単価」は、過去の実績値を大まかに用いて大雑把にコストを算定する方法ですが、あくまで大きなグルーピングごとに実績金額を示すだけのもので、もし結果が予算(目標コスト)を上回った場合などにおいて、コストと設計内容を結びつけてコストコントロールすることができません。したがって、「坪単価方式」は、信頼性とコストコントロールへの適応性が欠如していることから、コスト管理における概算手法としては採用を避けるべきです。また、施工者が工事受注のためにおこなう概算についても、当然「坪単価」の採用はリスクが大きすぎることになります。
基本的には、コスト管理あるいは工事受注を目的とした概算方式としては、項目ごとに数量を算出しそれに単価を乗じる「積上げ方式」が採用されることになります。設計の各段階ごとに、設計情報のレベルに応じてグルーピングされた項目・数量・単価により、一定の精度を有する概算コストが算定されます。
ただし、積上げ概算で算定された金額を検討する場合、実績値である類似案件の坪単価を、チェック用の参考値として使用することは有効と考えられます。
以下で、プロジェクトおよび設計各段階における設計情報と概算見積手法について述べます。また、概算見積について具体的に学びたい方は、(公社)日本建築積算協会が発行する「建築プロジェクトにおけるコストマネジメントと概算」をお読みください。
事業構想段階の概算見積
発注者が建築事業(プロジェクト)の立ち上げを検討するきっかけは二つあります。
一つ目は、土地の有効活用です。保有する土地に建物を建て経済的な果実を得ることで、土地の所有者が自ら事業を始める場合や、事業会社やゼネコンなどが土地所有者に提案する場合、あるいは定期借地権の活用など様々なケースがあります。賃貸マンションや賃貸ビルなど個人の相続税対策として提案される場合もあります。
二つ目は、資金と事業計画があり購入する土地を選定する場合です。分譲マンションが代表的な例です。
いずれの場合も、建物の事業収入と支出のバランスにおいて、適切な経済メリットがなければ事業がスタートできません。このように、事業が成立するか否かの可能性を検討する「フィジビリティ・スタディ」においては、建築工事費が重要なファクターとなるのです。
この段階では、類似建物の「坪単価」でコストを算定することが多くみられます。しかし、基本的に事業を進めるためには収支のバランスが成立し、経済的メリットを生み出すことが必須であり、工事費の上限も定まってきます。このように定められた予算内で事業が成立するためには、確実に収益を生み出す建物のレベルやグレードが必要となります。つまり、収益を生み出す建物の価値と事業予算との整合性を確認することが、フィジビリティ・スタディにおいては重要となるのです。そのため、大まかではありますが、建物の基本的なアウトラインを定めて、「積上げ方式の概算」によりコストを算定し予算と計画建物のレベルを整合させることが、事業成功への最も重要で有効なプロセスとなります。
企画設計段階の概算見積
事業のスタートにあたり、建物の概要を定めるのが企画設計です。敷地に対してどのように建物を配置するか、全体の規模や用途や建物機能別のおおまかな配置などの全体計画を定めます。
構造方式や大まかな仕上げグレードなどを設定し、基本的な構成要素について数量を算出し、合成単価を乗じてコストを算定します。数量は床面積当りの歩掛を使用するケースも多く、算定されたコストは一定の誤差を含んだものとなります。概算コストが予算を上回っていた場合は、設計内容をおおまかに変更するなどのコストコントロールをおこないます。
建物形状の検討、地下有無の検討、構造形式の検討など、基本的な建物内容に関する複数案の比較検討もこの段階で行うことが効果的です。
基本計画段階の概算見積
基本計画段階においては、建物のおおよその内容が検討され、基本的な建物仕様が決定される最も重要な段階です。したがって、極力精度を高めた概算を目指す必要があります。
基本計画段階の設計情報については明確に規定されていませんが、一般的には平面・立面・断面図などの必要図面と概略仕上表、構造概要と設備概要などが整理されています。設計者とのコミュニケーションに留意して、できるだけ設計情報を充実させることが大切です。
構造に関しては仮定断面や数量歩掛あるいは主要項目の数量が設計者から示されることが一般的です。仕上げに関しては、主要項目の数量を設計図から計測・計算します。それぞれの項目に合成単価を乗じて概算金額を算定します。設備に関しては、電気容量や空調負荷あるいは床面積などの原単位に実績単価を乗じて概算金額を算定します。
概算コストと目標コストとの整合性を確認し、必要に応じてVEなどにより設計内容の変更などを行います。
建物形状、杭工法、構造形式、外部仕上、設備方式など複数案を比較検討し、最適解を追求する段階です。また最近は、地球温暖化防止への取り組みも社会全体で加速し、建物の建設におけるGHG(地球温暖化ガス)排出量の低減を義務付ける動きもあり、設計段階におけるコストマネジメントとともに環境マネジメントもますます重要になってきました。
基本設計段階の概算見積
基本設計は、建物に関する基本的な設計内容の全体像が確定する段階です。この段階で設計はほぼ固まり、実施設計へと進んでいきます。
基本設計段階においては、仕上表や建具概略図、構造伏図、部材断面図や杭概略図、設備機器概略図など設計情報も充実していきます。積算項目はかなり詳細化され、必要に応じてメーカーや専門工事会社から見積を徴集し検討します。
この段階で設計内容(概算コスト)と予算(目標コスト)とをきちんと整合させることにより、実施設計段階での手戻りを防止し、適正な工事発注へとつながっていくのです。
概算見積における合成単価
概算見積においては、設計情報が限られていることから、実施設計後の精算積算のように工種別の詳細な項目・数量を計測・計算することができません。したがって、代表的な項目あるいはその時点で計測・計算可能な項目について数量を算出し、これに複数要素の単価を乗じて概算コストを算定することになります。複数要素の単価をまとめたものを「合成単価」と呼びます。
各設計段階における設計情報のレベルに応じて、計上する項目とその数量に対応する合成単価を定める必要があります。
(1)躯体の合成単価例(コンクリート)
躯体コンクリート金額
=躯体コンクリート量(㎥) X 合成単価(生コン材料+強度補正+打設労務+ポンプ車損料)
(2)仕上の合成単価例(外壁タイル)
外壁タイル金額
=タイル面積(㎡) X 合成単価(下地モルタル+平面タイル+コーナー等役物(m/㎡)+ 壁伸縮目地・打継目地(m/㎡))
(3)仕上の合成単価例(屋上防水)
屋上防水金額
=屋上面積(㎡)X 合成単価(コンクリート金鏝+アスファルト防水(断熱材)+ コーナーキャント(m/㎡)+ 保護フィルム + ワイヤーメッシュ + 伸縮目地(m/㎡) + 押えコンクリート(㎥/ ㎡) + コンクリート金鏝
発注者側から見た概算見積の信頼性について

発注者として、設計段階における概算見積の信頼性を高めて、プロジェクトの予算管理をスムーズに進めるための考え方をご紹介します。
設計者のコスト管理と概算見積の留意点
企画設計、基本計画、基本設計の段階では実施設計(詳細設計)はまだ完了していないわけです。したがって、限られた設計情報で一定の誤差を含んだコストを算定する概算見積について、その特質や信頼性について十分理解しておくことが必要です。
発注者の予算(目標コスト)を有効に使い価値の高い(発注者ニーズを満足する)建物を設計するために、設計者は適切にコスト管理を行う必要があります。各設計段階ごとに積上げ方式による概算見積を行い、概算コストと予算との整合性を確認し、必要に応じてVEなどを活用して設計変更をおこなうなどコストコントロールを着実に進めることが重要です。
設計者は、算定した概算コストについて、極力一式計上を避け、内訳明細などによりその根拠を明確にして発注者に説明する必要があります。発注者が設計者の算定した概算コストを信頼して、コストコントロールにおける設計者の提案を迅速に検討し方向性を決定することが、建築プロジェクトの適正な進行にとって欠かせません。
「設計者の概算見積は余裕をみているから、このまま進んでも予算内での発注は十分可能だろう。」などと発注者が設計者の概算見積を信頼せず、提案にも理解を示さない場合には、工事発注段階でゼネコンの見積金額が大幅に予算を上回り、プロジェクトが頓挫する状況になるでしょう。
また、設計者が積算事務所などに概算見積を依頼したものの、概算コストが予算を上回っていたにも関わらず概算結果を尊重せず、設計内容を見直さないままに実施設計を完了したため、工事発注段階でつまずくこともよく見られることです。
上記のように、せっかく概算見積をおこなったものの、算定結果を信頼せず、コストコントロールに有効活用できないケースも多いのです。その結果、プロジェクトを中止しないまでも、実施設計完了後の大幅な設計変更で建物価値を著しく低下させ、さらに労力や時間を大きく浪費することも珍しくありません。このように、発注者側の意識と設計者側のコスト管理に対する姿勢は、プロジェクトの成否に大きく関わるのです。
総合建設会社(ゼネコン)から提出される概算見積の留意点
前述したように、ゼネコンが概算見積をおこなう場合、以下のような営業的状況が考えられます。
(1)発注者が実施設計前の段階で施工者を決定し、また工事費についても確定したい。
ゼネコン側からすれば、設計が確定せず情報も限られた段階で工事費を確定することは避けたいわけです。しかし、営業的に辞退するわけにもいかない場合が多く、提出する見積書の内容にも工夫を要することになります。
- 金額は一式計上して、数量・単価を明らかにしない。実施設計段階完了後、見積金額の変更を制約するような根拠を極力出さない。
- 見積金額に、一定額のリスク対応費を含ませておく。
- 例:NET(事前原価)金額にリスク対応費を加える。提出金額にリスク対応費を加える。
- 物価変動その他のリスク要因や不確定の工事を別途にするなど、多くの防衛的な見積条件を記載する
上記のような見積書になることが多くみられます。
これに対して発注者側としては、まずは、一式計上を避けて、項目・数量・単価といった積上げ方式の内訳明細の提出を指示する必要があります。これについては、見積要項書あるいは公共工事(ECIやデザインビルドなど)における入札公告等において事前に明記しておく必要があります。提出された見積書が一式項目で構成されていたとしても、ゼネコン社内では基本的に詳細な積上げ積算を行ってNET(事前原価)を算定しています。したがって、内訳明細を提出するか否かは、技術的な問題ではなく営業的なスタンスとなります。
見積提出後に数量・単価が記載された内訳明細の提出を要請したとしても、提出されるとは限りません。したがって、タイミングを外した場合は、概算見積書の内容を十分検討できないことになり、施工者と工事費を確定するという本来の目的は十分達成されないことになります。
また、現時点で不確定な要素について明らかにし、今後の対応について協議しておくことが望ましいと考えられます。条件があいまいなまま、自己に都合の良いように押し切ろうなどといった考えは、現在では通用しません。発注者と受注者(施工者)が対等なパートナーとして協力することがプロジェクト成功に欠かせない要素として、グローバル的にも認識されています。
(2)設計施工あるいは特命発注において設計各フェーズで工事金額を確認する
設計施工の場合についても、提出される概算見積書については、前述したような一式項目で構成されるケースが多く見られます。したがって、項目・数量・単価といった積上げ式の内訳明細の提出を指示することは前述したとおりです。発注者側としては、設定内容の確認と概算工事費の妥当性について各フェーズにおいて適時確認しながらプロジェクトを進めていくことが必要です。
設計施工の場合は、本来発注者側でコスト管理を行うはずの設計者が施工者側ということになるため、CMR(コンストラクション・マネジャー)のように第三者的に発注者をサポートする体制も検討する必要があります。ゼネコンに過度に依存することなく、発注者側がプロジェクト全体をコントロールできる機能が必要となるのです。
概算見積を有効活用してコスト管理を進めよう
建築プロジェクトのコスト管理において、設計の各段階ごとに概算積算をおこない、設計内容と予算(目標コスト)との整合性を確認し必要に応じて設計内容を修正していくコストコントロールが重要です。そのためには、設計各段階の情報レベルに合わせた概算手法を選択し、必要な精度の概算コストを算定する必要があります。
このように、プロジェクト関係者が概算見積をタイミングよく適切に活用することにより、発注者が満足する価値の高い建物が実現し、建築プロジェクトは成功へと導かれるでしょう。