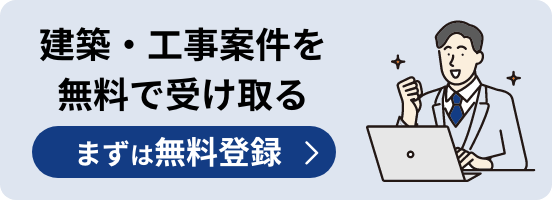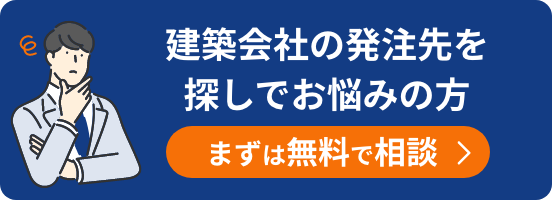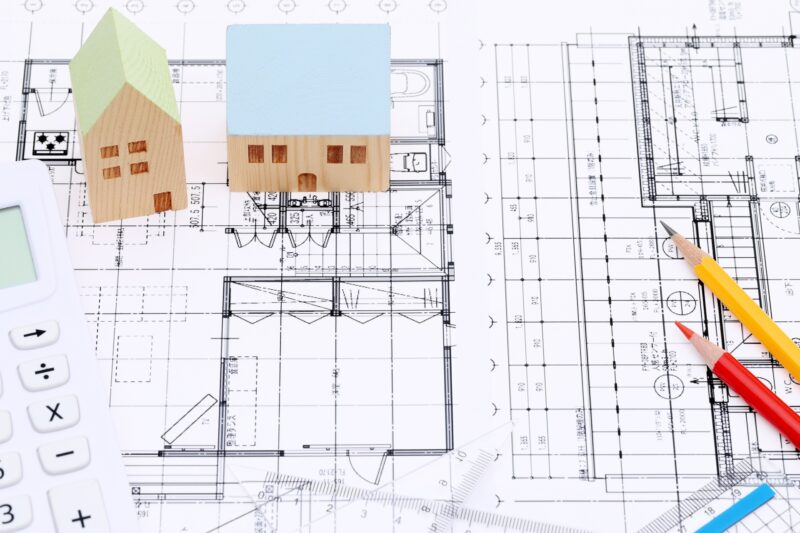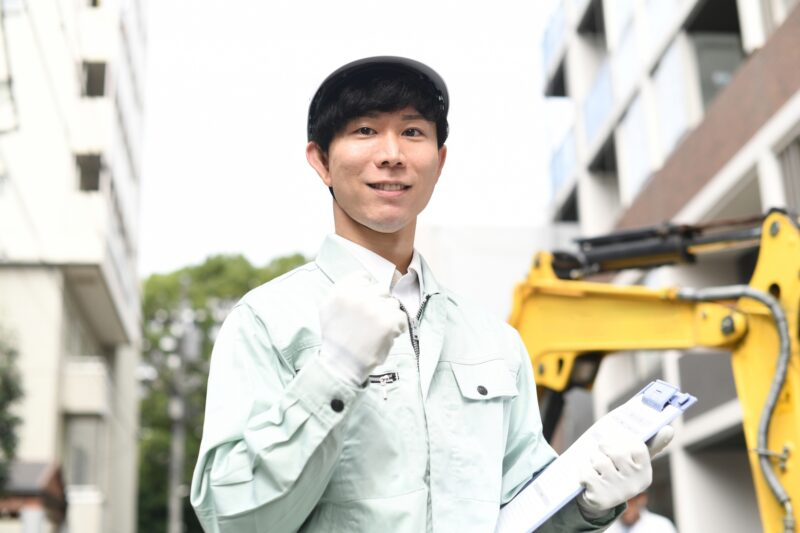設計の様々な段階において、設計者は積算をおこない工事費予算(目標コスト)との整合性を確認する必要があります。設計が完了していない段階でおこなう積算は「概算」と呼ばれ、予算と整合するよう設計を進めていく活動は「コスト管理」と呼ばれています。本記事では、コスト管理の概要と設計の各段階における概算および実施設計完了後の精算(詳細)積算について、発注者と設計者の視点で解説していきます。
コスト管理とは?
一般的に工業製品は、同じ品物が大量に工場で作られ、店頭で価格が表示されて販売されます。したがって、品物を手に取り価格を見比べて購入を決定しますので、消費者の満足度はかなり高いものとなります。
一方、建築物は、特定の敷地に合わせて一品ごとに受注する屋外生産品という特性をもっています。まず発注者のニーズを反映して設計図が作成され、それにもとづいて建設会社が工事費を見積り、発注者と価格交渉をおこなった後に請負契約を締結することになります。多くの発注者は、契約から1年あるいは数年後に実物の建物を手に入れることになります。
建築物の工事価格はひとつひとつ異なるとともに、建物が出来上がってみれば、発注者が支出する金額(工事価格)と発注者のニーズ(建物の価値)が整合しないというリスクも十分考えられるところです。したがって、発注者のお金を有効に使い、発注者にとって価値の高い建物を実現するためには、設計段階から専門家によるコスト管理をおこなっていくことが重要です。
(公社)日本建築積算協会では、「コスト管理とは、建築事業におけるコスト有効性を向上させるために、コストの目標を設定しその達成を図る、一連の管理活動である。」と定義しています。(新☆建築コスト管理士ガイドブック)
コスト有効性とは、建物の効用(アウトプット)を支出するコスト(インプット)で割ったものです。つまり、コスト有効性を向上させるというコスト管理の目的とは、発注者の予算(コスト)を有効に使って建物価値を最大化することといえるでしょう。
コスト管理は、建物の内容が決定される設計段階におこなうことがもっとも有効です。設計段階では主として設計者がコスト管理を担うのですが、発注者をサポートしてプロジェクトをマネジメントするCMR(コンストラクション・マネジャー)が関与するケースもあります。
設計段階の積算とは?
コスト管理は、目標コスト(予算)を定め、建物の主要な構成要素に適正にコスト配分する「コストプランニング」と、配分されたコストが具体的に設計へと反映されているかを確認し、コストと設計内容が不整合の場合は是正をおこなう「コストコントロール」で構成されています。
企画設計、基本計画、基本設計といった設計の初期から中期の各段階において、積算をおこない、積算金額が目標コスト以内であるか確認していきます。積算金額が目標コストを超過した場合は、VE(バリュー・エンジニアリング)などにより、設計内容を修正するか、場合によっては目標コストの見直しをおこないます。
このような実施設計(詳細設計)前におこなう積算を「概算」と呼びます。設計途中の限られた設計情報にもとづきおおよその数量や金額を算定するための積算ですので、概略の積算つまり「概算」と呼ばれるのです。
「概算」の詳細については、以下の記事を参照してください。
また、「VE(バリュー・エンジニアリング)」については、以下の記事を参照してください。
設計段階の積算が必要なタイミングと内容
設計の各段階における積算(概算)内容と、その活用の仕方について解説します。
企画設計段階の概算
事業のスタートにあたり、建物の概要を定めるのが企画設計です。敷地に対してどのように建物を配置するか、全体の規模や用途や建物機能別のおおまかな配置などの全体計画を定めます。
構造方式や大まかな仕上げグレードなどを設定し、基本的な構成要素について数量を算出し、合成単価を乗じてコストを算定します。数量は床面積当りの歩掛を使用するケースも多く、算定されたコストは一定の誤差を含んだものとなります。概算コストが予算を上回っていた場合は、設計内容をおおまかに変更するなどのコストコントロールをおこないます。
建物形状の検討、地下有無の検討、構造形式の検討など、基本的な建物内容に関する複数案の比較検討もこの段階で行うことが効果的です。
基本計画段階の概算
基本計画段階においては、建物のおおよその内容が検討され、基本的な建物仕様が決定される最も重要な段階です。したがって、極力精度を高めた概算を目指す必要があります。
基本計画段階の設計情報については明確に規定されていませんが、一般的には平面・立面・断面図などの必要図面と概略仕上表、構造概要と設備概要などが整理されています。設計者とのコミュニケーションに留意して、できるだけ設計図およびそれ以外の設計情報を充実させることが大切です。
構造に関しては仮定断面や数量歩掛あるいは主要項目の数量が設計者から示されることが一般的です。仕上げに関しては、主要項目の数量を設計図から計測・計算します。それぞれの項目に合成単価を乗じて概算金額を算定します。設備に関しては、電気容量や空調負荷あるいは床面積などの原単位に実績単価を乗じて概算金額を算定します。
概算コストと目標コストとの整合性を確認し、必要に応じてVEなどにより設計内容の変更などを行います。
建物形状、杭工法、構造形式、外部仕上、設備方式など複数案を比較検討し、最適解を追求する段階です。また最近は、地球温暖化防止への取り組みも社会全体で加速し、建物の建設におけるGHG(地球温暖化ガス)排出量の低減を義務付ける動きもあり、設計段階におけるコストマネジメントとともに環境マネジメントもますます重要になってきました。
基本設計段階の概算
基本設計は、建物に関する基本的な設計内容の全体像が確定する段階です。この段階で設計はほぼ固まり、実施設計へと進んでいきます。
基本設計段階においては、仕上表や建具概略図、構造伏図、部材断面図や杭概略図、設備機器概略図など設計情報も充実していきます。積算項目はかなり詳細化され、必要に応じてメーカーや専門工事会社から見積を徴集し検討します。
この段階で設計内容(概算コスト)と予算(目標コスト)とをきちんと整合させることにより、実施設計段階での手戻りを防止し、適正な工事発注へとつながっていくのです。
実施設計段階の概算
実施設計段階においては、基本設計からの設計内容変更とそれによるコスト変動についてモニタリングをおこなっていきます。各設計段階において、コストコントロールにより設計内容の変更がおこなわれてきましたが、実施設計段階では、今までに採用した変更内容を元に戻すことや仕様確定時にグレードアップするなど、設計完了に向けて駆け込み的にコストアップ要因が発生する例も多くみられるため、この段階でも気を抜くことはできません。実施設計中盤以降において、基本設計段階の概算をブラッシュアップするなどのコストチェックに留意する必要があります。
民間工事では、実施設計完了時に精算(詳細)積算をおこなう事例は非常に少ないことから、概算によるコスト確認をおこなった後、建設会社に見積依頼をおこなうような流れとなります。
実施設計完了後の精算(詳細)積算
前述したように、大部分の民間工事においては、実施設計完了後に設計者が精算(詳細)積算をおこなうことはありません。建設会社に見積を依頼し、その内容をチェックし、価格交渉をおこなって請負金額を決定することが一般的です。
一方、公共工事においては、入札時の予定価格(請負額の上限値)を設定するために精算(詳細)積算をおこないます。一般的に設計者に積算を業務委託し、設計者は積算事務所に再委託することが多くみられます。
基本的に、「公共建築工事積算基準」「公共建築数量積算基準」「公共建築工事内訳書標準書式」などの各種基準に準拠し、単価については公共発注者の指定単価や刊行物掲載単価を使用します。一般的な単価以外の項目については、専門工事会社やメーカーから見積を徴集し、定められた掛率(値引き率)を乗じて採用単価を決定します。あるいは必要に応じて複数の項目を組み合わせた「代価表」で単価を作成することもあります。
公共工事においては、基本的に数量および金額についての根拠が重視されるため、発注者が定めたルールにもとづいて積算を進めることになります。
なお、原則として、金額算定は発注者がおこなうことになっていますので、設計者は通常参考価格として直接工事費の算定までをおこないます。発注者側の金額算定は、「RIBC2」という公共工事金額算定システムを使用することが多くみられます。
発注者が活用する設計から発注段階までの積算

発注者が建築プロジェクトの予算管理を円滑に進めるために、設計から発注段階までの積算を有効に活用する方法について解説します。
設計段階の積算によるプロジェクト予算とスケジュールの管理
設計段階の積算は、建築主のプロジェクト予算およびスケジュールの管理において非常に重要です。
設計期間中に予算と設計内容をきちんと整合させておかないと、実施設計完了後に建設会社の提示する工事費見積金額が予算を超過することになり、プロジェクトの内容やスケジュールが大幅な軌道修正を余儀なくされるケースもあります。
特に重要なのが、「各設計段階における積算(概算)とコストコントロール」です。
ご紹介した4つの設計段階で概算をおこない、設計内容とコストを整合させていけば、的確なコスト管理が可能になります。
設計者は、設計の各段階において適切な概算手法を選定し、発注者の信頼を得られるよう概算金額の精度を高めることにより、設計内容の変更や予算の修正など発注者が意思決定を迅速におこなえる環境を整備する必要があります。発注者は、設計者と価値感や情報を共有し、予算内でスケジュール通りに目的に合った建物が設計・発注されるよう協働でプロジェクトを進めることが大切です。
特に、需要供給のバランスが崩れた状況においては、設計者が算出した「コスト」と建設会社の見積金額である「プライス」が大きく乖離することもあり、発注者と設計者は「コスト」と「プライス」の関係を理解することも重要です。
発注者側における「コスト」とは、適正な企業利益を含めた工事価格であり、論理的な積上げ積算により算定された金額を言います。
一方、「プライス」とは、建設会社が営業的な判断で提出する見積金額であり、需給関係や特命・競争などの発注要件などにより変化する非論理的な金額を言います。ダンピング価格や逆に高額な見積価格など発注者側の考えるコストと大きく乖離する場合もあります。
発注者側のコスト管理のベースとなる金額は「コスト」ですが、最終的に工事発注する場合は建設会社の見積金額である「プライス」が「コスト」を上回らないように発注の戦略・戦術を検討する必要があります。
実施設計後に建設会社へ依頼する工事費見積
公共工事においては、一般的に、実施設計完了後に設計者が精算(詳細)積算をおこない、算定された工事費をベースに予定価格を設定します。受注者の決定は、複数の建設会社が工事費の総額(一本金額)のみを提出する「入札」をおこない、予定価格以下で最も入札金額の低い建設会社が選定されます。ただし、不当に安い工事費は品質低下等を招くとして、低価格の入札(ダンピング)は失格とされることが一般的です。入札は一本金額ですが、通常、建設会社は精算(詳細)積算により事前原価(NETなどと呼ばれます)を算定し、入札金額を決定します。
民間工事においては、一般的に複数の建設会社に工事費の見積を依頼します。これを「見積合わせ」と言いますが、各社見積書の内容(内訳明細)をチェックし、内容の確認や価格交渉をおこなって契約先を決定します。見積内容のチェックなどは設計者がおこなうことが一般的ですが、設計施工(建設会社が設計と施工を担当)の場合などは発注者をサポートするCMR(コンストラクション・マネジャー)がおこなう場合もあります。また、価格交渉においては、設計者や建設会社のVE(バリュー・エンジニアリング)提案により設計変更するなど予算内に工事費を納める技術的な努力もおこなわれます。
民間工事においては、公共工事と異なり発注者が自由に請負契約先を決定することができますので、各建設会社の見積金額の順位に関わらず様々な交渉や内容検討をおこない、プロジェクトに適したパートナーを選定することが重要です。
設計段階の積算により予算とスケジュールの管理をスムーズに
ここまで、建築工事の設計段階の積算とコスト管理について解説してきました。
各設計段階の積算は、プロジェクトのコスト管理と適切な工事発注のための非常に重要な役割を果たします。
特にプロジェクトの予算とスケジュール管理をスムーズにして予定期間内に着工するためには、各設計段階で着実に積算をおこない設計内容と予算を整合させ、工事発注段階での手戻りをなくすことが効果的です。