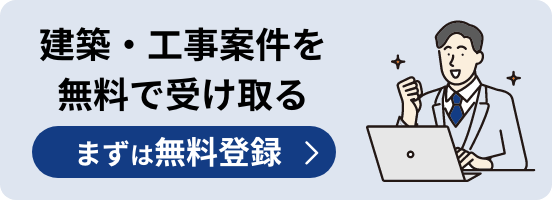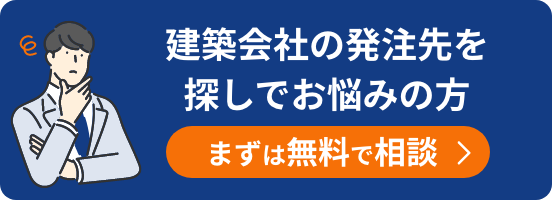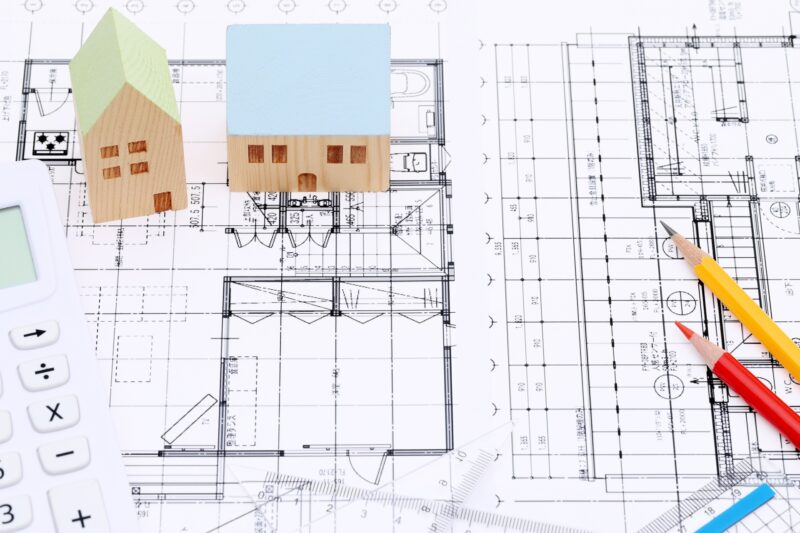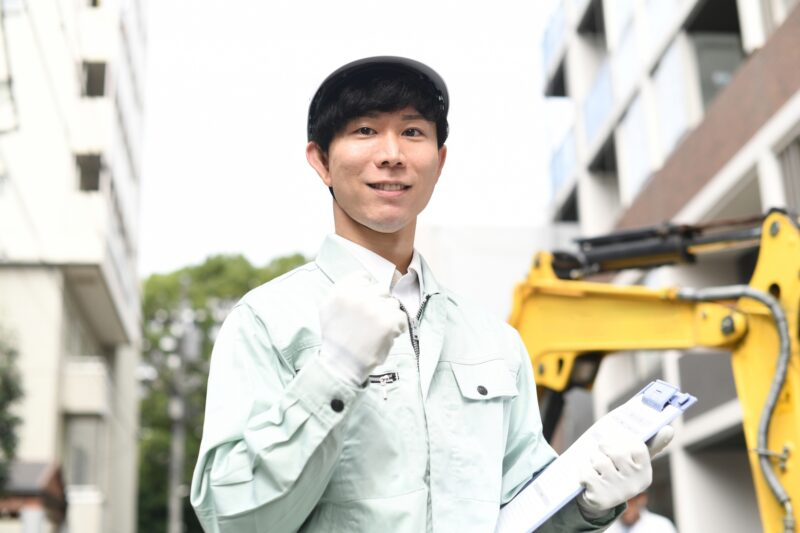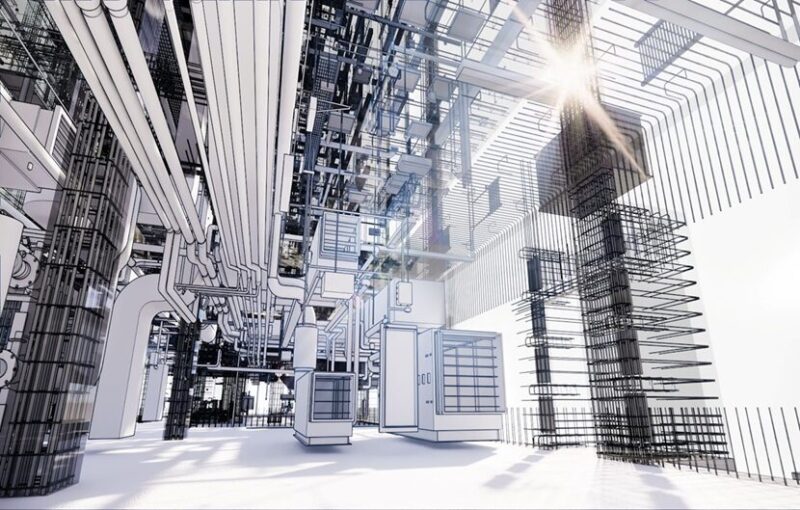建設業法は、すべての建設業者が従うべき重要なルールを定めた法律です。ルールの中には罰則を伴うものもあるため、建設業者はその内容をしっかり理解しておかなくてはなりません。また、工事請負契約に関する内容や建設業者の許可要件や評価内容も定められていますので、発注者にとっても理解しておく必要がある法令となります。
この記事では建設業法の主なルールや罰則について、わかりやすく説明していきます。
建設業法とは
建設業は、我々の日常生活に密接に関連する産業であり、インフラの発展や都市の形成において中心的な役割を果たしています。この業界の発展とともに、品質の確保や公正な取引、環境への配慮など、様々な課題や要求が生まれてきました。
建設業法は、これらの課題に対応するために制定された法律で、建設事業の公正な取引の確保や品質の向上を目的としています。この法律の背景には、戦後の高度経済成長期における建設ブームや、それに伴う品質低下や不正取引の問題が浮上してきた歴史があります。これらの問題を解決し、信頼性の高い建設業界の形成を目指して、建設業法が施行されることとなりました。
現代においても、建設業法は業界の健全な発展をサポートし、消費者や社会全体の利益を守るための重要な役割を果たしています。
歴史的背景
建設業法が制定されたのは1949年です。戦後復興に向けて数多くの建設プロジェクトが行われる一方で、過当競争やダンピングの受注、不適正施工などの問題が顕在化しました。
こうした問題に対応するために制定された基本的なルールが、建設業法というわけです。
建設業法の目的
建設業法の目的は、建設業法第1条に規定されています。
| この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
建設業法は、『①建設業者の資質向上』及び『②建設工事請負契約の適正化』を通して、以下の3つの目標達成を目指します。
- 「建設工事の適正な施工の確保」
- 「発注者の保護」
- 「建設業の健全な発達」
またこれらを通して「公共の福祉の増進」を実現することが建設業法の最終的な目的です。
なお①の「建設業者の資質向上」は、建設業者の許可制や行為規制を定めて財務基盤やガバナンス体制の整備を促すことを指しています。
また②の「建設工事請負契約の適正化」では、請負事業者にとって不合理な内容の契約が結ばれないために、建設工事請負契約に定めるべき事項や、契約条件に関する規制などを定めます。
建設業法の対象となる人
建設業法の対象は、建設業を営む者や関連する者です。これには、建物、道路、橋などの建設・修繕業務を請負う者、または建設資材製造業者や登録経営状況分析機関、登録講習実施機関、指定試験機関等が含まれます。
この法律に基づく許可や義務が適用されるため、対象となる建設業者は一定の資格や技術的基準を満たす必要があります。これにより、建設業界の品質と信頼性の向上が図られています。
建設業法に規定された主なルール
建設業界は、公共の利益をもたらすと同時に、多大なリスクを伴う産業です。建設業法は、この業界の健全な発展と安全性の確保のため、大きく分けて「建設業の許可制」「請負契約に関する規制」「主任技術者・監理技術者の設置」という3つのルールを設けています。
建設業の許可制度
建設業法における「建設業の許可制」は、建設業者が一定の基準を満たすことで、業務を適正に行える能力を有していると認められるための制度です。
建設業法第3条によると、建設業を営もうとする者は「軽微な建設工事のみを請け負う場合」を除いて建設業の許可を受けなければなりません。
ここでいう軽微な建設工事とは、以下の要件を満たす工事です。
- 契約金額工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
- 建築一式工事で工事1件の請負代金の額が1,500万円未満、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事のみ行っている工事
なお建設業許可は、「大臣許可と知事許可」の2種類と「建設業法別表第一の29業種」の組み合わせで取得します。
【大臣許可と知事許可の違い】
- 大臣許可…複数の都道府県に営業所を設ける場合
- 知事許可…ひとつの都道府県内のみに営業所を設ける場合
【建設業法別表第一の29業種】
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロツク工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゆんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
許可制度が導入されていることで、建設工事の発注者は、許可を受けた事業者が一定の信用性と能力を有していることを確認し、一定の安心感をもって取引を行うことができます。
請負契約に関する規制
請負契約に関する規制は、建設工事の品質を確保し、発注者(注文者)と請負人(建設業者)間の不平等を是正するために設けられています。
具体的な内容には、たとえば以下のようなものが挙げられます。
- 「契約時に定めるべき内容の指定」
- 「不当低い請負代金の禁止」
- 「不当な使用資材等の購入強制の禁止」
- 「著しく短い工期の禁止」
- 「一括下請けの禁止」
「契約書に記載すべき内容」が定められていますが、主に以下の内容です。
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工期
- 請負代金の支払時期と支払方法
- 工事を施工しない日や時間の定め
- 設計変更や条件変更時の工期・請負代金額の変更又は損害の負担やその算定方法
- 価格等の変動又は変更に基づく工期・請負代金額の変更やその算定方法
- 損害賠償に関する定め
- 契約に関する紛争の解決方法
これらが契約の時点で明確にされることで、発注者・請負人双方の権利義務が明確化され、公平な取引関係が確立されます。また一連のルールは、契約や工事内容をめぐり予期しないトラブルを未然に防ぐうえでも役立つものです。
また、近年は、建設資機材の供給不足や価格高騰あるいは建設現場の担い手不足など建設業の持続的発展が懸念されるような状況となっています。このような観点から、公平な取引を推進すべく建設業法に以下のような内容が定められました。
- 発注者は、工期や請負代金額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあるときは、契約前に建設業者へその情報を伝えなければならない。
- 建設業者は、主要資材の供給の著しい減少、価格の高騰など工事・請負代金額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあるときは、契約前に発注者へその情報を伝えなければならない。
- 前項の通知をした建設業者は、価格高騰などに際して工期・請負代金額などの変更について協議を申し出ることができる。
- 前項の協議の申し出を受けた注文者は、申し出が根拠を欠くなどの正当な理由がない場合は、誠実に協議に応ずるよう努めなければならない。
主任技術者・監理技術者の設置
主任技術者・監理技術者の設置制度は、建設工事の品質と安全性を確保するための仕組みです。
【主任技術者】
原則として戸建住宅と長屋を除くすべての工事現場に置かれる、施工の技術上の管理責任者
【監理技術者】
請負金額4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の下請契約を締結した工事で、主任技術者に代わって配置される責任者
これらの技術者は、工事の施工状況を監督し、品質が確保されているか確認する役割を担います。このため主任技術者や監理技術者は、特定の資格や実務経験を持った人から選ぶ必要があります。
建設業法の罰則について
建設業法は、業界の健全性を維持し、社会的信用を確保するためのルールです。もし違反行為があった場合、厳格な罰則が適用されます。具体的な罰則の内容は以下の通りです。
- 指示及び営業の停止(建設業法第28条)
- 許可の取消し(第29条)
- 営業の禁止(第29条の4)
- 監督処分の公告(第29条の5)
- 刑事罰(第45条〜第55条)
建設業法のどの条文に違反したかによって、上記のうちどの罰則が適用されるかが変わります。たとえば刑事罰の場合はこのようになります。
| 違反の内容 | 刑事罰の内容 |
| ・無許可で建設業を営む・特定建設業の許可がないのに下請契約を 結ぶ・営業停止、営業禁止処分に違反する・不正に建設業許可を取得する | ・違反者に3年以下の懲役または300万円 以下の罰金 ・法人に1億円以下の罰金 |
| ・主任技術者、監理技術者を設置しない・報告義務違反、虚偽報告・検査の拒否、妨害、忌避 | ・違反者に100万円以下の罰金・法人に100万円以下の罰金 |
法律に違反すると、罰則だけでなく事業の信用失墜や社会的制裁も受ける可能性がありますので、常に法令を遵守する姿勢が求められます。
建設業法を理解して、ビジネスを健全に成長させましょう
建設業法は、建設業界の健全な発展と、その業務を通じての社会的信用の維持を目的としています。建設業者は、これらの法律を遵守することで、持続的な成長と、長期的な信用の確保が可能となります。また、発注者も公正な取引と建設業界の持続的な発展のために建設業法を遵守することを求められています。