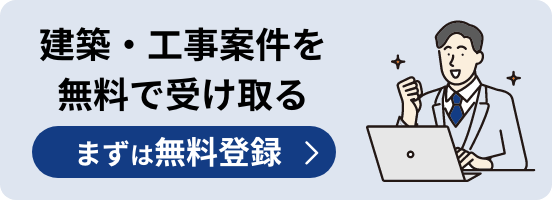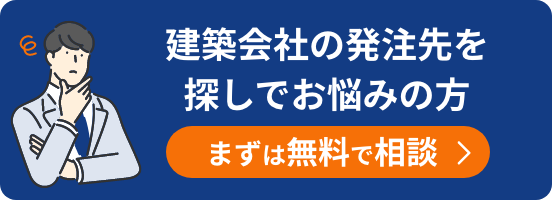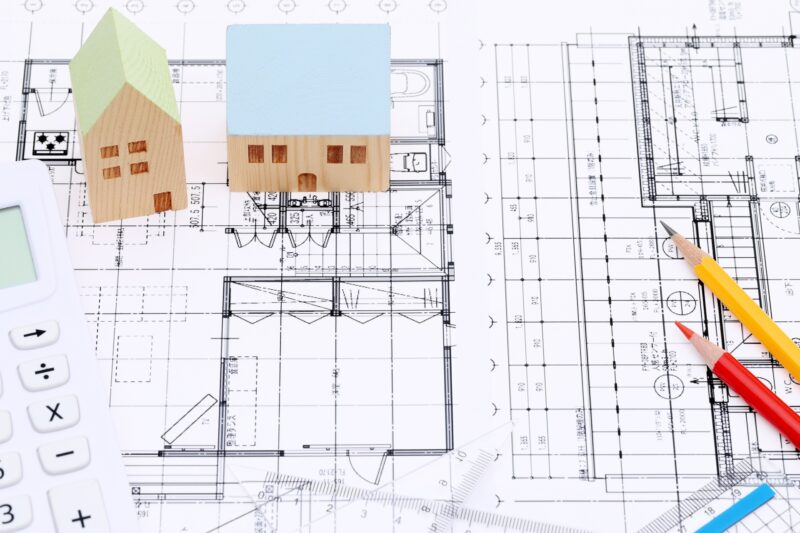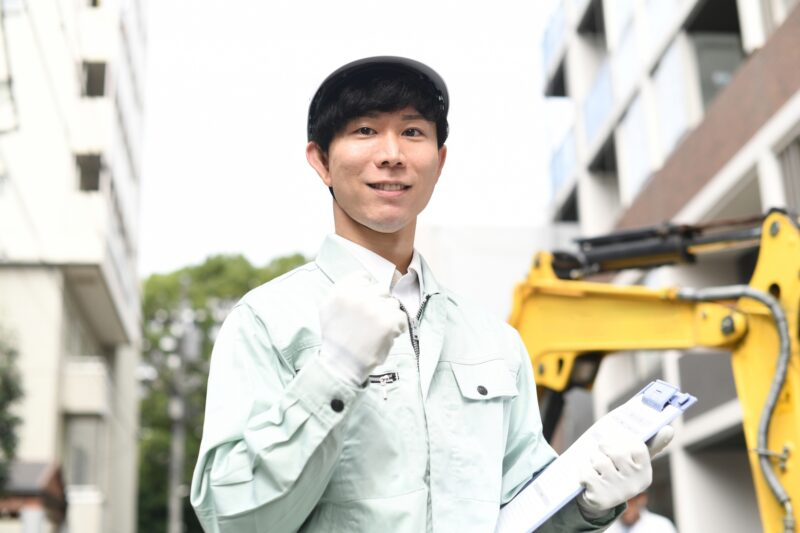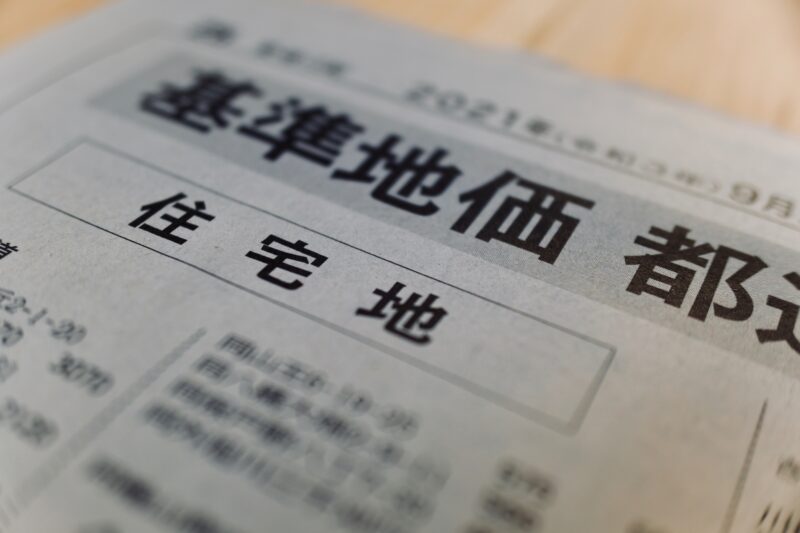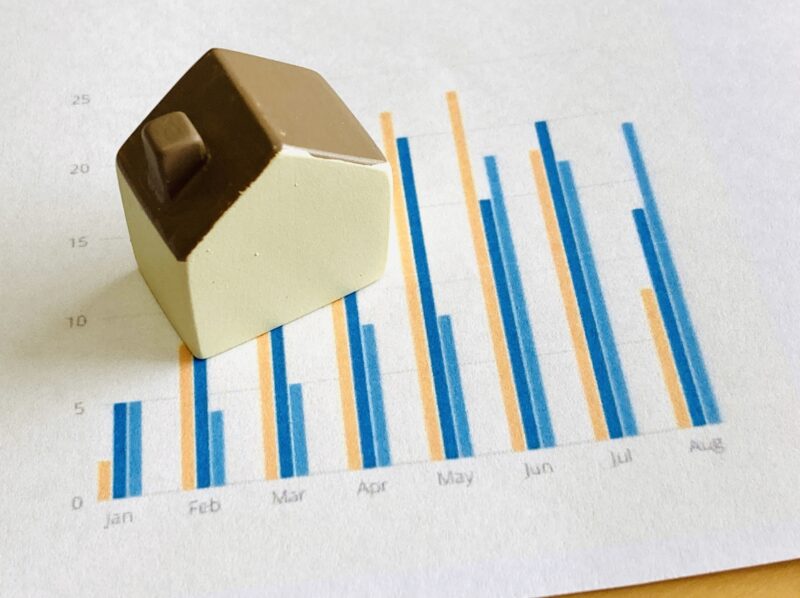新築で建築物を建てて検査を受けると「検査済証」が発行されます。ですが、検査済証がどうして発行されるのか、検査済証にどのような役割があるのかについて知らない人も大勢います。この記事では検査済証の概要と重要性について解説していきます。
民間事業者に特化した建築発注プラットフォーム「タチドコロ」は、様々な建築物に対応できる設計事務所や建設会社を探す事が可能。条件に合った複数の会社と同時に比較・交渉ができるだけでなく、WEB上でのマッチングに加えて、専門のコンシェルジュが受発注業務をサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
検査済証とは?
検査済証は建物の建築工事と深い関係があります。具体的には、その建築物が建築基準法などの各種ルールに違反していないことを証明するものです。
法律上の義務
検査済証についてのルールは、建築基準法のなかで次のように定められています。
第7条第1項:建築主は、建築工事の完了後に「国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請」しなければなりません。
第7条第4項:申請を受けた建築主事や自治体の職員は、建物が「建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査」します。
第7条第5項:検査で「建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付」します。
つまり検査済証の発行(と、その前提となる完了検査)は法律上の義務ということです。ちなみに建物を建築する際は着工前に「確認検査」という検査を受けて合格する必要があるため、検査済証は確認検査と完了検査という2種類(場合によっては「中間検査」を含む3種類)の検査をクリアした証ともいえます。
検査済証の記載項目
検査済証には、主に以下の項目が記載されます。
- 確認済証番号
- 確認済証発行年月日
- 建物物の場所(地名、地番)
- 建物物の主要用途
- 建物物の規模、階数、構造、面積
- 検査年月日
- 検査担当者名氏名
建築の流れについて
建物の建築には、いくつものステップを踏む必要があります。なかでも特に重要なステップとなるのが「建築確認」「中間検査」「完了検査」の三つです。
Step1 建築計画
↓
Step2 事前審査
↓
Step3 建築確認
事前審査が終わったら「建築確認申請書」を提出して建築確認(書類審査)を受けます。書類に不備がなければ、申請から7日以内(木造2階建て以下の一戸建て住宅)、もしくは35日以内に「確認済証」が交付されると定められています。
また、一定規模以上の建物は、構造計算適合性判定あるいは省エネ適合性判定を受ける必要があり、それぞれ35日か28日の範囲内で期間が延長されます。ただし、確認検査機関によっては、これらの期間を短縮しているところもあり、また審査によって設計図の修正などの期間が加算されることもあるため注意が必要です。
なお確認済証の交付を受けるまで工事に着工することはできません。
↓
Step4 着工
↓
Step5 中間検査
一定規模以上の建築物は、「特定工程」と呼ばれる段階まで進んだ段階で「中間検査申請書」を提出し、中間検査を受けます。この検査は主に目視や実測で行われます。申請書を提出するのは特定工程に係る工事が完了してから4日以内です。また申請から4日以内に審査が行われ、合格後速やかに「中間検査合格証」が交付されます。なお交付を受けるまでは次の工程に進めません。
↓
Step6 竣工
↓
Step7 完了検査
建物の完成後4日以内に「工事完了届」を提出して、完了検査を申請します。申請から7日以内に検査(主に実際の建築物と図面の比較)が行われ、合格後速やかに「検査済証」が交付されます。
↓
Step8 引渡し
検査済証の役割
検査済証が実査に必要となる(役立つ)のは以下のようなケースです。
住宅ローンの申込み
住宅の新築購入では、多くの場合「住宅ローン」が利用されます。この際に、ほぼ必須ともいえるのが検査済証(および確認済証)です。一般的な金融機関では住宅ローンの申込み段階で確認済証を、ローンの実行段階で検査済証の提出を求めています。
さらに、賃貸向けの不動産の新築で「投資用ローン」を受ける際も検査済証が必要です。
不動産の売却
検査済証の有無は不動産の売却にも大きく影響します。なぜなら中古不動産売買の「重要事項説明」には、検査済証に記載されている「検査済証番号」と「確認済証発行年月日」が必須だからです(ちなみに確認済証の「建築確認番号」も必須項目です)。
なお、個人が不動産会社に売却する場合や個人間で不動産取引をする際には重要事項説明の必要はありません。仮に検査済証がなくても売却は可能です。ただ検査済証は「建築物が建築基準法に適合していることの証明」なので、取引相手に不安を抱かせないために、また有利な条件で取引を行う上でも非常に大きな役割を果たします。
住宅リフォームや増築
一定条件や、一定規模以上の増改築には「建築確認申請」が必要です。そして建築確認申請を行う際は検査済証が必要になります。つまり家の間取りが変わるような大がかりなリフォームは、検査済証がなくては行えません。
優良な取引先を探しているなら、複数の気になる会社と同時に比較・交渉が可能な建設に特化したマッチングプラットフォーム「タチドコロ」をお試しください。
検査済証が「ない」場合について
完了検査は建築主の義務ですが、現実にはさまざまな理由により、完了検査を受けていない(=検査済証がない)建築物が少なくありません。最後に、そのようなケースについて説明します。
検査済証がなくても問題ない場合
すでに説明した通り、検査済証は住宅ローンを組む際にほぼ必須で、不動産の売却や住宅リフォームでも必要になるケースが大半です。ただし「ただ住むだけ」「人に貸すだけ」であれば、検査済証の有無が問題になることはありません。また所有者から直接建築物を購入する場合も、(建築基準法に適合していない可能性があるという)リスクを気にしなければ特に問題ありません。
ちなみに建築確認(上記のStep3)は建築工事を進めていく上で必須です。建築確認に合格した証拠である「確認済証」は基本的にすべての建物に交付されているはずなので、もし確認済証がない建物であれば取引は行わない方が無難でしょう。
検査済証は後から発行できる?
完了検査を受けていない建物について、後から完了検査を受けることはできません。つまり検査済証の発行を後から受けることは不可能です。こうしたケースでは、そのままでは増改築や大がかりなリフォームができません。
ただし、既存建築ストックを有効活用するための「救済措置」は存在します。国土交通省の「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」は、完了検査に代わる「建築基準法適合状況調査」の制度と手順を示したものです。
具体的には「建築確認図書」(確認済証と添付図書)、もしくは建築士が作成する「復元図書」に基づいて指定確認検査機関が目視や実測で検査を行い、法適合状況調査の報告書を作成します。この報告書は検査済証と同じではありませんが、増改築時の添付資料としての利用が可能です。
検査済証を紛失したら?
完了検査を受けて検査済証を交付されていたものの、それを無くしてしまうケースも少なくありません。残念ながらこの場合も再発行は不可能です。
ただし一度は検査を受けているため、その記録は管轄の行政庁(市区町村)に残っています。窓口で申請をすれば「台帳記載事項証明書」を発行してもらえるため、そこに記載されている情報から増改築の申請手続などが可能です。
建物を建てるときは検査済証について正しく理解しましょう
今回は検査済証の概要や役割について説明しました。特に検査済証と確認済証の違いについてはしっかりと理解しておきましょう。また検査済証がないケース・紛失したケースについても説明しましたが、基本的に「完了検査は建築主の義務」です。これから建物を建てる人は、必ず完了検査を受けて、検査済証の交付を受けるようにしてください。
民間事業者に特化した建築発注プラットフォーム「タチドコロ」は、様々な建築物に対応できる設計事務所や建設会社を探す事が可能。条件に合った複数の会社と同時に比較・交渉ができるだけでなく、WEB上でのマッチングに加えて、専門のコンシェルジュが受発注業務をサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。