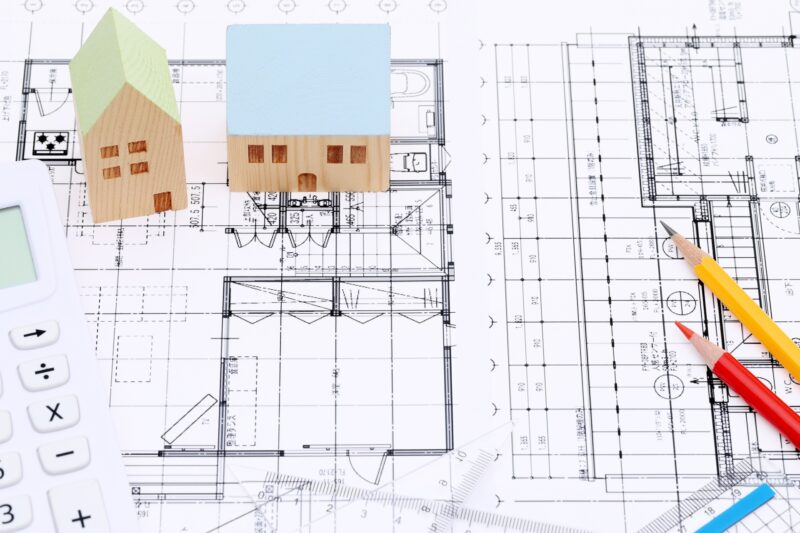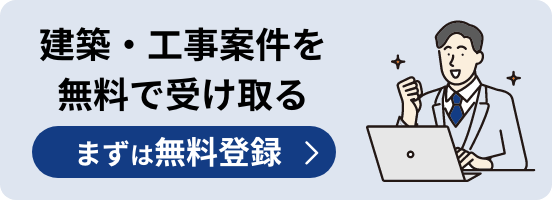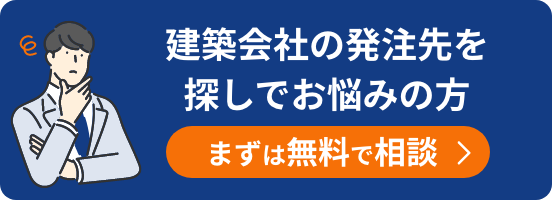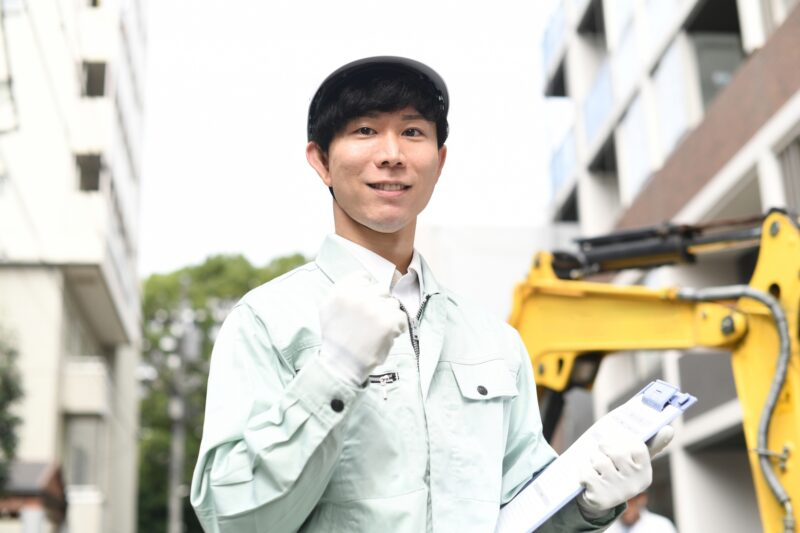VEとは建築物の機能や性能を予算と発注者の要求レベルに合わせて最適化し、工事費用を低減することを目的とする手法です。設計段階、発注段階、施工段階それぞれの局面でVEの手法を用いた交渉が可能ですので、建築プロジェクトのコストコントロールのために積極的に活用しましょう。
工事のVEとは?
建築工事の金額交渉の過程では、VE(ブイ・イー)という言葉がよく使用されます。
VEとは「Value Engineering(バリュー・エンジニアリング)」の略称で、当該建築物に必要な機能を保持しながらコストを低減する、あるいは予算の範囲内で機能を向上させるなど、発注者が投資するコストに対して最大の価値を獲得することを目的とする管理手法です。
発注者にとっての価値(Value)を高めるための方策として、機能(Function)と支払った費用の総額(Cost)との対比により価値向上を進めていくことになります。
VALUE(価値)=FUNCTION(機能)/COST(費用)
VEによる価値向上には、以下のパターンがあります。
- コスト低減型(能率性の改善)・・・同じ機能のものを安いコストで手に入れる。
- 機能向上型(有効性の改善)・・・同じコストでより優れた機能を手に入れる。
- 複合型(有効性の改善)・・・より優れた機能をより安いコストで手に入れる。
- 拡大成長型(戦略性の改善)・・・少々コストは上がるが、それ以上に優れた機能を手に入れる。
VEの手法によるコスト削減過程においては、設計図通りの品質を維持することが原則となります。
設計段階において第三者のチームや設計者によるVEを行なったり、設計や施工段階において建設会社からVE提案を受けるなどの例が多くみられます。
CDとの違い
コスト調整のもうひとつの手法として、CD(シー・ディー)もよく使用されます。
CDとは「Cost Down(コスト・ダウン)」の略称で、機能の低下を伴う材料仕様などの変更や、一部の工事項目の取りやめや規模の縮小などでコストを削減することを目的として行われる手法です。
CDは、VEでは実現不可能なレベルの金額を削減するためや、VEへの理解不足などの要因があり、ゼネコンや専門工事会社からのVE提案には機能や品質を下げるCD提案が含まれることが少なくありませんので注意が必要です。
VEの誕生と公共建設工事への導入
VEが誕生するきっかけとなったのは1947年,アメリカのGeneral Electric(GE)社で起こった「アスベスト事件」です。
第2次世界大戦後の当時,アスベストは不燃材料として火災を予防するために多くの建物で使用されていました。GE社の製品塗装ラインの床にも多く使用されましたが,戦後間もないこともあり入手困難でした。そこで,資材担当であったL.D.マイルズ氏は,火災が起きたときに延焼を防ぐ別の材料がないかどうかを専門業者に相談したところ,アスベストよりも安価な代用品が手に入ることが分かりました。ところが,GE社内の消防規定で「アスベストを使うこと」が決められているため,その代用品を使えません。
そこでマイルズ氏は、新材料での防災実験を行い、代用品でも十分に防火できることを証明しました。そして社内の消防規定を変え,この代用品を使用することで,大幅なコスト削減に成功したのです。
この時マイルズ氏は、「我々が欲しいのは材料や部品そのものではなく、その『働き』すなわち『機能』である」ことを発見したのです。その後、マイルズ氏が開発したVE手法は、米国の企業や政府機関に急速に広まっていきました。
わが国に導入されたのは1960年頃で、製造業を中心に普及していきました。建設業界においては、大手クラスのゼネコン数社が導入し、積極的に活用を進めましたが、業界全体に広く普及するには至りませんでした。
また、1990年代から公共工事の建設費縮減が重要課題となり、公共建築工事の設計段階におけるVE手法の活用が検討され、1997年から第三者チームによる設計VEの試行が実施されました。その後、入札段階におけるVE提案付き入札、契約後の工事段階におけるVE奨励付き発注が実施されました。
公共工事におけるVEの活用
- 設計段階におけるVE 改善案(設計改善案)
- 原設計に対してVE チームがコストコントロールおよび設計改善案の手段として活用します。
- 提案付入札(技術競争型)
- 原設計に対して入札者が改善案の検討を行い、その内容を盛り込んだ金額で応札します。
- VE奨励条項付発注(施工コスト節減型)
- 契約時の設計図書をもとに受注者が改善案を検討し、提案を行います。受注者には節減額に応じた額が報奨として還元されます。
民間工事におけるVEの活用
民間企業の発注工事においては、主に発注者予算に合わせるための手法としてVEの手法が用いられます。
VEは設計の各段階や工事発注時(請負契約前)に用いられることが多く見られ、VEやCDあるいは値引き交渉などを経て請負金額が決定されます。たとえば工事見積が予算オーバーだった場合などに、建設会社や専門工事業者にVE提案を要請するケースなどもあります。また、建設会社あるいは専門工事会社(下請企業)が施工段階において自主的にVEを活用することもあります。
民間工事でVEを実施するタイミングは?
民間企業の発注工事でVEを実施するタイミングは、発注時に限った話ではありません。
設計段階や施工段階においても、VEの手法が大きな効果を発揮する場合があります。
設計段階のVE
設計者により、基本計画・基本設計・実施設計段階からのVE検討が行われます。特命発注のように施工者が決まっている場合などは、建設会社に見積とVE提案を求めることもあります。
設計の初期段階であればVE提案を実施設計図に反映させることが可能になるため、正式見積時でのコストダウンが期待できます。
工事発注段階のVE
工事の見積を取得し、契約候補となる建設会社をターゲットとして最終の金額交渉のためにVE提案を求めます。設計段階においてコストコントロールが不十分であった場合には、「VE/CD」を含めて請負金額を交渉することになります。
また、発注者側が見積書の内容を検討して適正と判断した金額を提示するなど、様々な価格交渉により請負金額が決定されるのです。
建築工事段階のVE
工事の進行中であっても、建設会社からVE提案を受けることもあります。
この場合には、請負金の変更を伴うこともありますが、施工方法などについてのVEは、請負金の変更を伴わない原価低減のため、建設会社独自で行うことがあります。
主に施工者都合のコスト調整(コストダウンによる収益改善)を目的として提案されることが多いため、性能や仕様を落とす(CD)結果にならないかどうか、VE提案の採用には慎重になる必要があります。また、VE削減額に対して施工者への報奨金(削減額の半分など)を配慮するなど、公共工事と同様の仕組みによって施工者の提案意欲向上を図ることも、結果的には発注者の利益に繋がります。
追加工事費用の捻出のため、やむなく発注者都合でVE提案を要請するケースもあります。
VE提案の実例
VEでは、内装の壁紙や床の変更から構造方法の変更まで、大小さまざまな手法が考えられます。ここでは、建築工事のVE提案の実例をご紹介します。
【事例】渋谷地下街改修計画(Ⅱ期)床工事(設計原案)
| 設計原案 | 既存のタイル仕上げを撤去し、新たに下地よりタイルを張り替える設計 |
| 問題点 | 全面通行止めにはできず、撤去時の騒音・振動粉塵の発生および養生期間の長さ(1~2 日)等の懸念事項が予測 |
| VE案 | 既存タイルの上に化学系下地調整材 にて下地処理した後、ゴムタイルで仕上げる工法を採用 |
| VE効果 | ・通行止めにせず、夜間工事のみで完了・原設計より▲53,600千円コストダウン |
参照:一般社団法人 日本建設業連合会 2022年度VE等施工改善事例発表会
VE案の採否を決めるポイント
VEによるコストダウン手法を、より効果的に実行するポイントについて解説します。
金額交渉の前にまずVEを実施する
工事発注段階で発注者側がコスト調整を試みる場合は、以下の手順が考えられます。
- 見積書の精査(適正数量・単価・金額の検討)と適正金額の交渉
- VEとCD案の検討
- 値引き等の交渉
段階を踏んだ交渉により、建築工事の品質確保と施工業者との良好な関係を維持できるメリットがあります。
できるだけ上流でVEを実施する
設計がある程度進行すると、抜本的なVE提案は難しくなります。
発注者側の希望するコスト内に収めるためには、基本計画・基本設計段階から設計者を中心にVEを行うことが重要です。早い段階であれば、建築ボリュームの見直しなど抜本的な検討も可能です。
維持管理コストを考えるとトータルで損をすることもある
VE提案は初期費用を抑えるためだけの内容になりがちです。
そのVE提案を採用する事によってランニングコストが増える可能性はないか、LCC(ライフサイクルコスト)の視点で原設計との比較検討をすることも必要です。
建築工事の予算管理にVEを活用しましょう
ここまで建築工事のVEについて、その意味と手法、効果的な導入方法などについて解説してきました。
単純な値引き要請だけでは、建設会社との信頼関係はなかなか構築できず、結果として施工の品質も落ちてしまう恐れがあります。
VE手法は、根拠のある金額調整の手法であり、発注者と受注者が対等の立場に立ったフェアな取引であると言えます。
建築プロジェクトのコストコントロールのためには、計画の早期の段階からVEの手法を取り入れると、より効果を発揮できるでしょう。