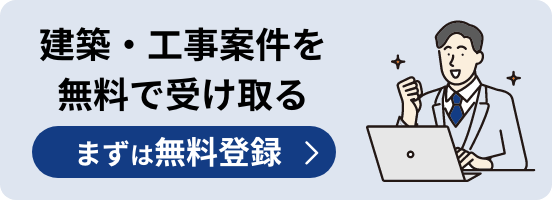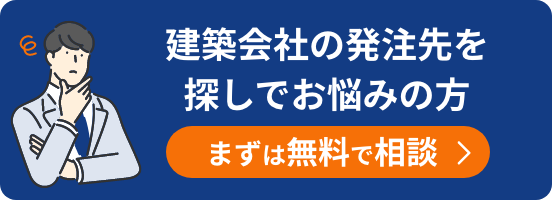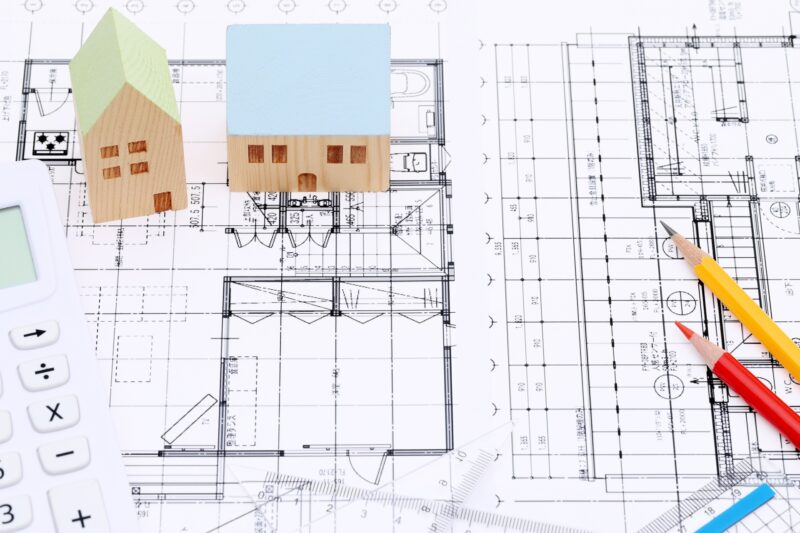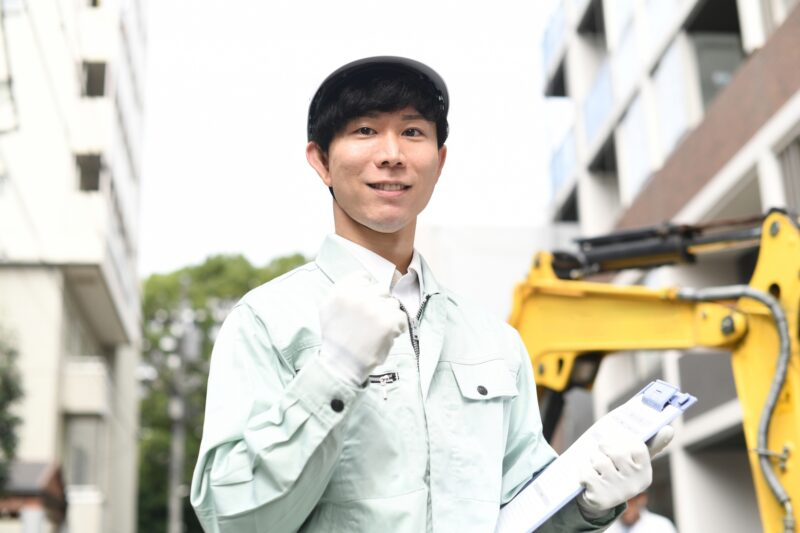建築工事で施工不良が発覚すると、発注者からのクレームを受けるだけでなく手戻り工事になり工事の利益を大幅に落としてしまいます。原因を担当者のせいにするのではなく、施工不良を発生させないための対策を社内で構築することが何より大切です。
建築工事の施工不良の事例
建築工事の施工不良が発生すると、施主からのクレームになるばかりでなく、手戻り工事が発生して工事原価も余計にかかることになります。
建設会社の信用も失墜し、その後の受注にも大きく影響するため、チェック体制を構築して施工不良を防がなければなりません。
まずは、施工不良の代表的な事例を部位ごとに見ていきましょう。
施工不良の事例①躯体工事
鉄筋コンクリートの打設不良によるジャンカやコールドジョイントは目視でも分かりやすく、クレームに発展しやすいケースです。
鉄筋工事と型枠工事、設備工事など、関連するすべての工種が連携して打設計画を入念に練る必要があります。
建物の水平・垂直の精度が悪く、傾きが見られる事例もあります。内外装工事でごまかしたとしても、将来的に発覚して大きなトラブルを招く可能性が高いため、躯体工事段階で精度を高めることが必須です。
鉄骨造や木造の現場では構造金物の不足や取付不良が見られるケースもあり、工事管理者だけでなく複数の目でのダブルチェックが欠かせません。
施工不良の事例②外装工事
引き渡し後に雨漏りが発生すると大きなクレームに発展します。
屋根や屋上防水の施工不良による雨漏りだけでなく、強風雨時には外壁やサッシ周辺から雨水が浸入してくることもありますので、施工時だけでなく、工事完了後に放水試験を実施するなどして入念にチェックをする必要があるでしょう。
また、サイディングやタイルなどの外壁材の反りや剥離が問題となる場合もあります。メーカー保証を受けるためには規定通りの施工がなされていることが条件となるため、施工マニュアルを遵守するだけでなく下地施工状況の写真をしっかりと撮影しておくべきです。
施工不良の事例③断熱工事
部分的な結露やカビの発生で建物の断熱材の欠損が発覚することがあります。
引き渡し後に断熱材が剥離したり脱落したりしないように、自社の施工マニュアルを示し施工者に周知させましょう。
目視によるチェックだけでなく、サーモカメラなどの計測機器を用いて施工品質を検証することも有効です。
施工不良の事例④仕上工事
床や壁紙の施工時のキズは、引き渡し後のキズと明確に区別するために、施主完了検査で入念にチェックし記録に残しておきましょう。予防策を怠ると、引き渡し後に発生したキズを当初からのものとされてしまい、無償で修繕しなければならなくなることもあります。
手すりなど人間の力がかかる部品や、吊り棚などの壁付け部品の下地施工忘れは、引き渡し後に脱落して建物内事故に発展する危険があります。最悪の場合は訴訟にまで発展する場合もありますので、その部品に応じて適切な下地を施工するように徹底しなければなりません。
施工不良の事例⑤設備工事
排水配管のつなぎ忘れや接続施工不良による漏水は、マンションなどの場合は階下に被害を及ぼし大きなクレームにつながります。
設備業者の施工時点では問題が無くても、その後の内外装工事の際に傷つけられて設備配管や配線が損傷してしまうケースもあります。完了検査では実際に使用する人の動作と目線で、時間をかけて入念に使用チェックをしなければなりません。
施工不良が発生する原因
施工不良を防ぐためには、検査で指摘して是正することはもちろんですが、その発生する根本的な原因を把握することが重要です。
その原因を追究して、自社に不足している要素を改善しましょう。
作業者の技術不足
施工不良が発生する最も多いケースは、施工を行う作業者の技術が不足している場合です。たとえば、図面や仕様書を良く読まない、あるいは理解せずに作業をしているケースが典型でしょう。
この場合は作業者の技能や知識を向上させるよう、指導をしなければなりません。
管理担当者の知識不足
現場監督や各専門工事の作業主任者の施工知識が不足していることもあります。
チェックしなければならない要所が分かっておらず、施工不良を見逃してしまっては管理者の職務を果たせていないことになります。
社内チェック体制の不備
社内での検査体制が十分でなく、現場任せになっているケースもあります。
検査の役割は、施工者以外の客観的な目でチェックし、中で実際に仕事をしている人間では気付かない箇所を指摘することです。
そもそも客観的な検査ができる人材が社内におらず、現場の人間のみで完結しているケースもあるかもしれません。
無理な工期と実行予算の設定
工事に与えられた工期が少なく、チェックを受ける前に次工程に進んでしまう場合もあるでしょう。
その場合は、複数の職種を同時に詰め込み過ぎて十分な作業体制が取れていない可能性があります。
工事の実行予算を過少に設定してしまい品質を確保するための適正な発注ができていない場合も、施工不良が発生しやすくなる要因です。
関連記事:建設工事の実行予算作成について分かりやすく解説!実行予算で注意するポイントも説明します
施工不良を防ぐためのポイント
発覚した施工不良を取り上げて担当者を責めるだけでは根本的な解決にならず、会社のレベルアップにもつながりません。
ここでは施工不良を防ぐために有効なポイントをいくつかご紹介します。
クレーム事例のフィードバック
施工不良によるクレームは、その場限りの対処にならないよう、社内および協力会社間で内容を共有しましょう。
施工不良の事案と原因、対策方法を1枚の紙に簡潔にまとめるなどして施工不良事例集を作成し、定期的に読み合わせをすることも有効な方法です。
技術・知識の向上
施工技術や知識の向上のために、社内および協力会社間で技術仕様の説明会を開催し、施工不良のフィードバックをします。
社外のセミナーや勉強会へ参加することも大切ですが、参加した担当者が自社に持ち帰り学んだことを共有することが大切です。同業他社との交流も積極的に行い、情報交換をしましょう。
社内検査体制の確立
施工不良を未然に防ぎクレームを無くすためには、要所を抑えた社内検査体制の確立が必須です。
チェックするポイントおよび検査の方法を明記した「検査チェックシート」を用意して活用するようにしましょう。
社内リソースが不足している場合は、第三者検査機関や民間のホームインスペクション(住宅診断)業者に検査を依頼する方法もあります。
適正な工期と金額での受注
不適切な工期と金額での受注は、施工不良を引き起こす一番の原因ともいえます。
受注を優先した営業主導の工期・原価設定にならないように、見積および積算の精度を向上して現実的な工期と工事原価を設定することは何よりも大切なことです。
社内一丸となって施工不良を防ぎましょう
施工不良を防ぐためには、品質の確保を作業者や管理担当者任せにせずに、しっかりとしたフォロー・検査体制を構築することが大切です。
適切な工期や原価設定も施工不良を無くすために重要な要素ですので、社内および協力会社が一丸となっての取り組みが求められます。
「タチドコロ」は建設に特化したマッチングプラットフォームです。
専門家で構成されたコンシェルジュチームが発注者をサポートすることにより、施工不良を発生させない優良な建設会社と安心してお取引できる環境をご用意しております。