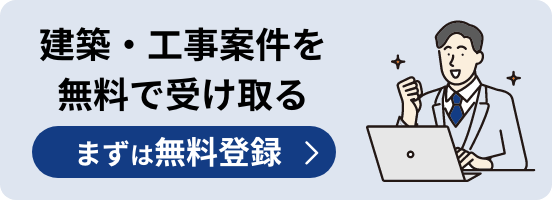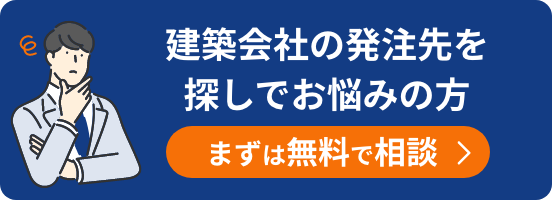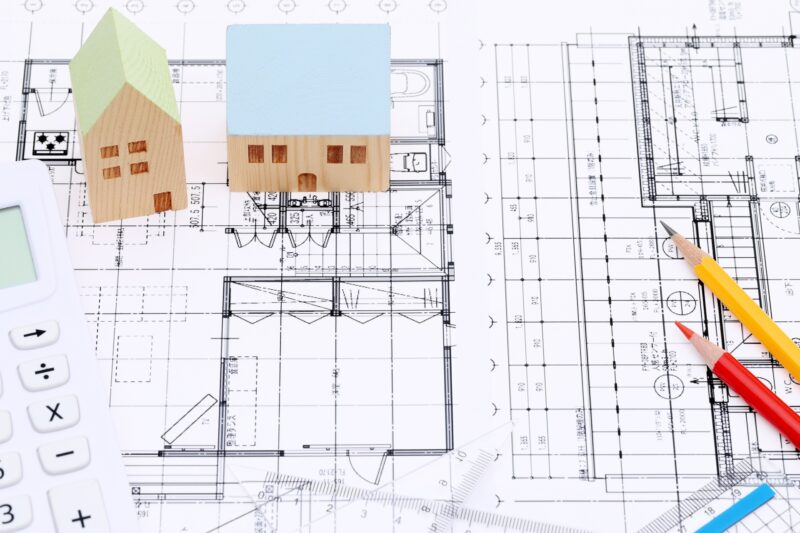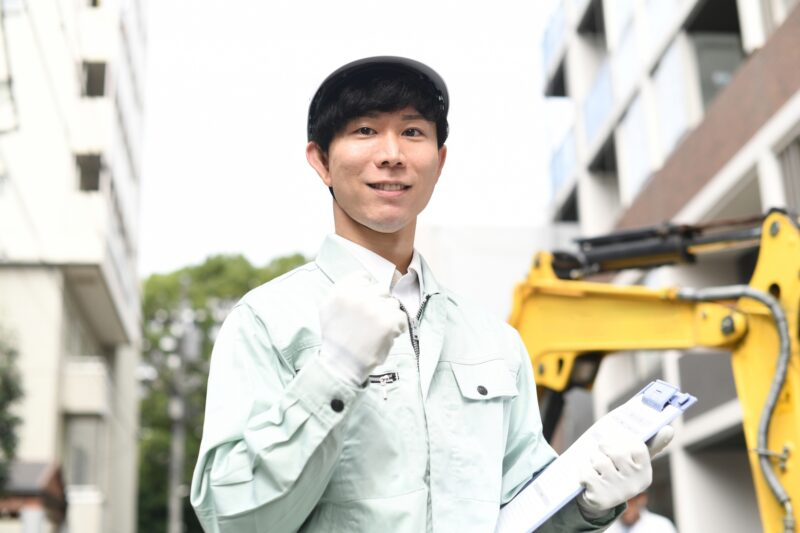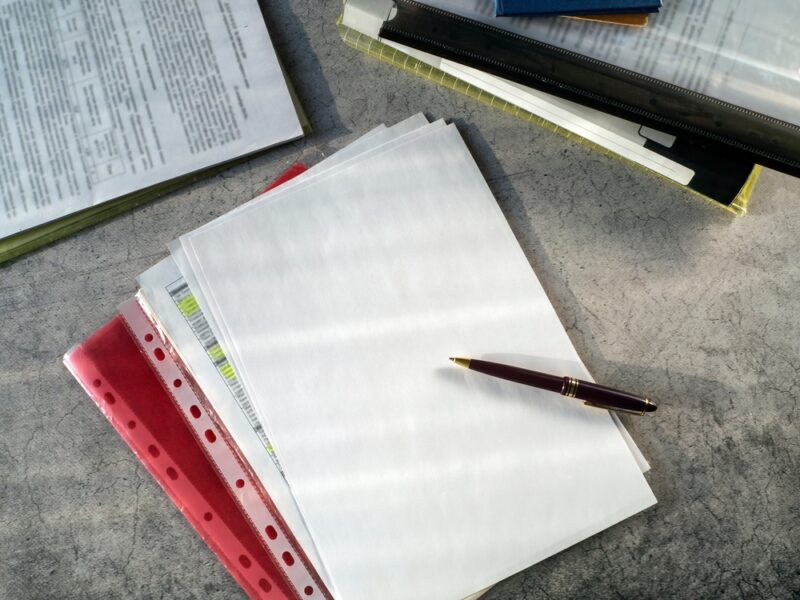契約保証金とは、契約履行を確実に担保するものとして、落札者が発注者に対して支払わなければならない金銭的な保障のことです。本記事では、間違われやすい入札保証金との違いやそれぞれの制度概要、また保証金が免除になるケースについて解説します。
民間事業者に特化した建築発注プラットフォーム「タチドコロ」は、様々な建築物に対応できる設計事務所や建設会社を探す事が可能。条件に合った複数の会社と同時に比較・交渉ができるだけでなく、WEB上でのマッチングに加えて、専門のコンシェルジュが受発注業務をサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
契約保証金とは?
公共工事の入札に参加して落札した際には「契約保証金」が発生することに注意が必要です。契約保証金の金額を認識していないと、資金不足で契約が不可能になる可能性さえもあるため非常に重要です。
契約保証金の概要
公共工事の契約をしようとする者は、発注者に対して契約の履行を担保するための保証金として契約保証金を納める必要があります。工事を予定通り完了させれば引き渡し時に返還されますが、契約の締結や履行をできなかった場合には契約保証金は国庫や自治体に没収されることになります。
国との契約の場合は、会計法に基づき契約金額の10%以上と定められており、自治体との契約の場合は条例で定める規定によりますが、国と同様に10%とする自治体が大多数です。工事金額によっては契約保証金も大きな金額となりますので、公共工事の入札に参加する際には必ず念頭に置く必要があるでしょう。
【契約保証金の算定例】
工事落札金額 8,000万円のケース
8,000万円 ✕ 10% = 契約保証金 800万円
契約保証金の納付方法と期限
契約保証金の納付には、現金あるいは有価証券の二通りの方法があります。
有価証券は国債や地方債などの債券や手形・小切手などを指しますが、いずれにせよ契約締結前に納めなくてはなりません。落札から納付まで1週間ほどしかないケースもあるため、資金の調達に注意を払う必要があります。
契約保証金が免除になるケース
契約保証金は受注金額によっては高額となるため、手持ち資金の確保と言う意味では可能であれば支払いたくないものです。
契約保証金が免除になるケースもありますので、その例を説明します。ただし、取り扱いは発注機関によって変わるため入札の要項書や規定等を事前によく確認しておきましょう。
①金額が少額である場合
国や自治体などの発注機関によって規定が異なりますが、予定価格が100万円〜500万円以下の少額工事の場合などには発注者のリスクが少ないとして契約保証金を免除とするケースです。
②契約の履行について保証が受けられる場合
発注機関を受取先とした、銀行の保証や保証事業会社による契約保証に加入している場合は金銭的担保が得られるため免除となる場合があります。後述する公共工事履行保証証券(履行ボンド)と併せて、契約保証を活用することによって初期投資を抑えることが可能になるでしょう。
③同様の契約を履行した実績がある場合
過去に同様の契約を履行した実績がある場合も免除になる可能性があります。過去2年に同様の契約の履行を2回以上していることが目安となります。
契約保証の活用
契約保証金免除条件のひとつである契約保証について詳しく解説します。この保証を提供する保証事業会社は、前払い金保証事業法で定められた要件を満たした東日本建設業保証株式会社など3社で、公共工事の前払い金の保証とセットで契約保証を行っています。また、同様の仕組みとして銀行による契約保証も活用されています。
契約保証のメリット
契約保証は、受注者の落ち度によって契約期間内に工事を完了させることができなかったり、既定の品質を満たせなかった場合などに、保証事業会社から発注者へ金銭的な補償金を支払うものです。
この保証制度を利用することによって、契約保証金を現金や有価証券で支払うよりもはるかに安価な保険料で済むことがメリットです。上手に活用すれば、契約保証金の金額に躊躇せずに高額な工事の入札にチャレンジするチャンスが広がるといえるでしょう。
ただし、保険料は掛け捨てとなりますので、経費が増大して若干工事の利益率を押し下げる可能性があることには注意が必要です。
契約保証の注意点
契約保証を提供するのは銀行や保証事業会社です。当然のことながら、保証には審査があり、企業の与信が問われます。契約時には過去の施工実績や決算状況などの書類提出が必要になり、場合によっては契約に必要な保険金額を満たせないケースもあります。また、企業ごとに与信枠が設定されているので、全体の限度額を考慮する必要があります。
落札から契約保証金の支払いまでの期日が短い場合には、迅速な保険契約が必要となります。保険契約に必要な書類関係を事前に準備しておき、速やかに保険申込をできるようにしておくべきでしょう。
公共工事履行保証証券(履行ボンド)
同様の制度として、損害保険会社が提供する公共工事履行保証証券(履行ボンド)と呼ばれる制度もあります。これは、発注者に対して保険会社が受注者と連帯して債務の履行を保証する契約です。発注者は、金銭的保証か、あるいは役務(≒工事の完了)の保証かを選択できます。
役務による保証を求められた場合は、保険会社は契約者と一体となって工事を完遂するために、他の建設会社を探して工事請負契約を結びます。
入札保証金と契約保証金の違い
契約保証金と混同されやすいものに「入札保証金」があります。この二つの保証金の違いについて解説します。
入札保証金
入札保証金は、国や自治体の行う入札に参加する場合に予定金額あるいは自らの入札金額の数%以上の保証金を事前に納めるという制度です。入札保証金の金額は発注機関により異なりますが、建設工事の請負に関しては予定価格の5%とする場合が多いようです。
契約意思のない者が安易に入札に参加したり、落札者が契約締結を行わないことによって事業スケジュールが延期になったり再入札のために経費が掛かるなど、発注者が受ける損害に備えるという意味合いがあります。
入札終了後の保証金の取り扱い
入札保証金は、落札できなかった場合には速やかに返金され、落札した場合は契約保証金を納付した後に返金されます。落札したにもかかわらず契約しなかった場合には入札保証金は没収されてしまいます。
入札保証金が免除になるケース
入札保証金が免除になるケースもあります。特に指名競争入札においては保証金免除としている自治体が多いようです。
また、契約保証金と同様に保証事業会社や銀行、損害保険会社が入札履行保証(入札ボンド)を取り扱っており、この保証契約を条件に免除となる場合もあります。
入札ボンド
入札保証金に代えて「入札ボンド」を導入する発注機関が増加しています。これは入札への参加資格として、保証事業会社や銀行、損害保険会社などの第三者による経営力評価を取り入れるものです。
発注機関に入札ボンドの提出を求められた企業は、入札前に財務的な履行能力を金融機関や保険会社に審査してもらい履行保証を受ける必要があります。
契約保証金と入札保証金を理解してリスクを回避
今回は契約保証金について制度の概要と納付方法、免除になるケースなどについて解説しました。公共工事の受注にあたっては、契約保証金や入札保証金制度を知っておくことは必須といえます。履行保証制度を利用する場合など免除になるケースもあるので、制度をよく理解して上手に活用することをおすすめします。
また、今回ご紹介したものはあくまで一般的なケースです。入札案件や発注者によってそれぞれ取り扱いが違うため、事前によく確認するようにしましょう。また、民間工事の場合は履行保証を求められるケースは少ないのですが、求められた場合にはこれに対応する仕組みも限られますので注意が必要です。
民間事業者に特化した建築発注プラットフォーム「タチドコロ」は、様々な建築物に対応できる設計事務所や建設会社を探す事が可能。条件に合った複数の会社と同時に比較・交渉ができるだけでなく、WEB上でのマッチングに加えて、専門のコンシェルジュが受発注業務をサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。