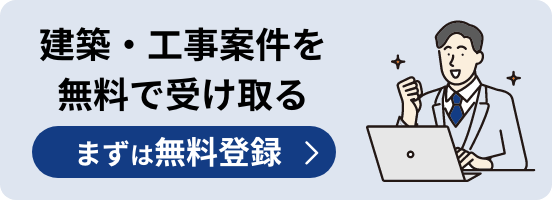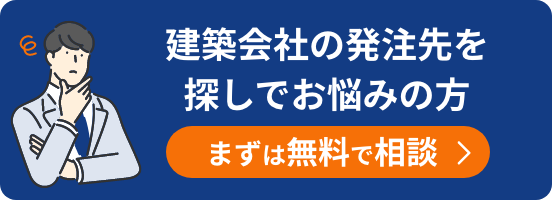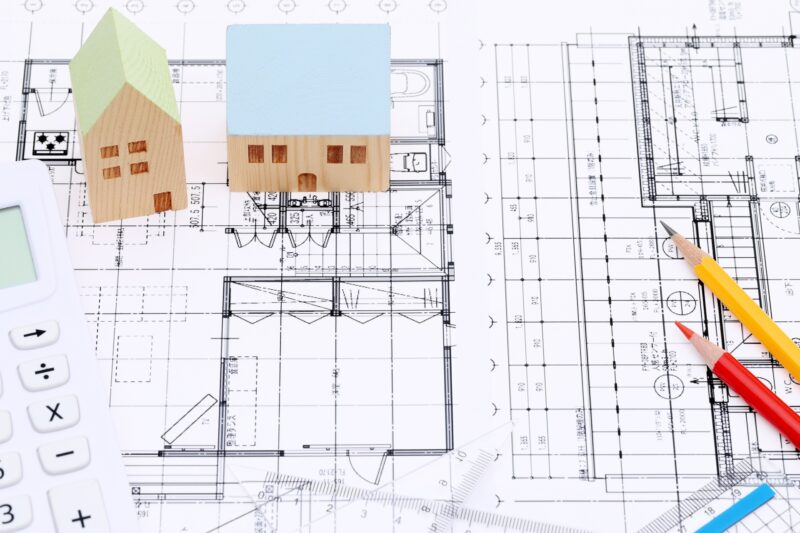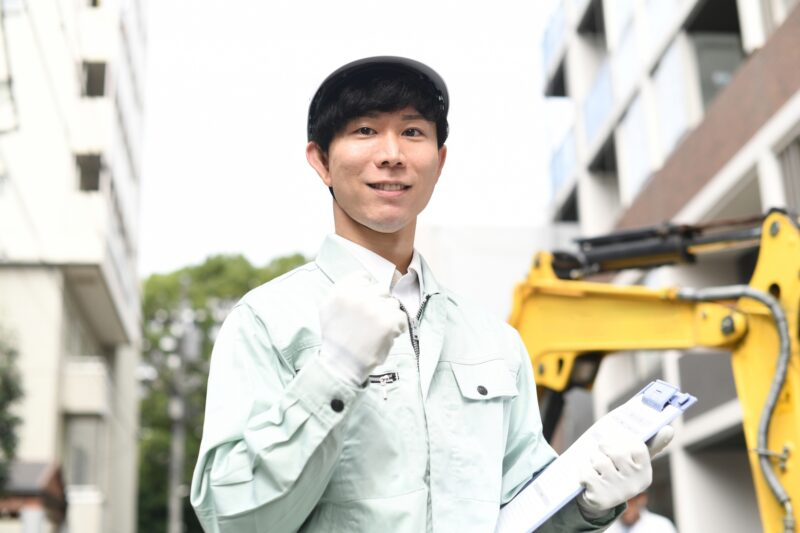建築コスト管理士と建築積算士にはどのような違いがあるのでしょうか?本記事では、それぞれの資格概要や取得難易度、どんな人が取得するのにおすすめなのかについて徹底解説します。
(公社)日本建築積算協会の資格認定制度
(公社)日本建築積算協会が認定する資格には、建築コスト管理士、建築積算士、建築積算士補の3つがあります。
一般的に資格を定義する場合は、どのような業務を行うかといった、業務内容や業務領域について規定されることが多くみられます。これに対して(公社)日本建築積算協会における資格の定義は「求められる技術」と「求められる知識」のみ規定しており、業務内容・業務領域については具体的に規定していません。これは、コストマネジメントや積算に携わる技術者が将来的に活躍の場を広げ、活動レベルが大きく飛躍することが可能になりつつあることに起因するものです。
以下の図にあるように、建築積算士補から建築積算士、そして建築コスト管理士へとスキルアップしていく基本的なキャリアパスが形成されていく仕組みとなっています。
建築コスト管理士とは?
建築プロジェクトにおけるコストマネジメントの重要性が建設産業界で広く認識されてきた2006年に、(公社)日本建築積算協会により建築コスト管理士認定制度が創設されました。「企画・構想から維持・保全・廃棄にいたる建築のライフサイクル全般に渡って、コストマネジメント業務に関する高度な専門知識及び技術を有する専門家」と定義されており、求められる技術としては「各フェーズに応じた工事費その他費用の算定、コストプランニング、コストコントロール」と規定されています。
また、建築積算の知識も合わせ持つ、建築積算士の上位資格として位置づけられています。
なお、5年ごとに資格更新があり、CPD(継続能力開発制度)で定められた研修ポイントの取得が更新要件となっています。
建築コスト管理士の仕事内容
建築コスト管理士は、建築プロジェクトを成功に導くため、事業企画の段階から設計や工事発注・施工そして竣工後にいたるまで、工事や維持保全などのコストに関するマネジメントを行います。
建築コスト管理士は、発注者を代行するCMR(コンストラクションマネジャー)や設計事務所あるいは施工者(ゼネコン)などの様々な職域で、限られた予算を有効に使い建物の価値を最大化するために、あるいは顧客満足度を高めながら適正利益を確保するためにコストマネジメントを行っています。
建築コスト管理士の試験概要
建築コスト管理士の試験は、建築積算士と同様に「(公社)日本建築積算協会」が実施しており、試験内容は以下の「求められる知識」をテキスト化した「新☆建築コスト管理士ガイドブック」の全て、および「新☆建築積算士ガイドブック」の指定部分から出題されます。
- コスト情報収集・分析
- 広範囲な市場価格(経済、建設産業、不動産他)
- 発注戦略(発注与条件、契約、入札手続きと評価他)
- 調達戦略
- フィジビリティースタディー
- 概算技法
- 施工技術・工期算定
- LCC・VE及びFM・PM・CM・PFIの概要
- 環境配慮
- 建築関連法規
- IT活用
さらに、建築積算士の上位資格として、「原則として、建築積算士に求められる知識を包含する」とされています。
なお建築コスト管理士試験は、次のいずれかの要件を満たしていれば、受験できます。
- 建築積算士の称号を取得後、更新登録を1回以上行った方
- 建築関連業務を5年以上経験した方
- 1級建築士に合格し登録した方
試験は一次試験と二次試験で構成されており、一次試験が学科試験(4択式)、二次試験が短文記述試験となっています。
合格基準点は、正答率60%程度がおおよその目安となることが公表されています。
なお、学科試験で一定の基準点を超えた者は、次年度から2年間は学科試験が免除されます。
建築コスト管理士の難易度
過去の建築コスト管理士試験の合格率は、以下の通りとなっています。
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 2024年 | 359人 | 146人 | 40.7% |
| 2023年 | 292人 | 160人 | 54.8% |
| 2022年 | 288人 | 138人 | 47.9% |
| 2021年 | 221人 | 140人 | 63.3% |
| 2020年 | 182人 | 122人 | 67.0% |
| 2019年 | 155人 | 128人 | 82.6% |
| 2018年 | 159人 | 118人 | 74.2% |
※公益社団法人日本建築積算協会による「建築コスト管理士認定事業による試験実施結果」 毎年の公表データから独自作成
建築コスト管理士の受験者は毎年増加していますが、合格率もかなり低下傾向にあります。現状は難関資格に近づきつつあるようですが、出題範囲と合格基準点が明確で、ホームページに過去問も公開されていることから、受験勉強しやすい資格ともいえるでしょう。
建築コスト管理士を取得するメリット
建築コスト管理士を取得することで、次のようなメリットがあります。
- CM(コンストラクション・マネジメント)や建築設計あるいはECI(Eariy Contractor Involvement)などの業務プロポーザルにおいて、多くのプロジェクトにおいては技術者の資格要件あるいは評価点の対象資格となっている。
- 建築プロジェクトにおいて、全体のマネジメントやコストマネジメントなどの重要な役割を担える能力が身につく。
- 就職や転職時に有利となる。
- キャリアアップや年収アップに役立つ。
近年は、大手企業が建築コスト管理士を昇進要件にする、あるいは資格取得を組織的に推進するなど、多くの企業においてコスト・積算技術者のキャリアパスに組み込まれることもみられ、受験者も増加しています。
建築積算士とは?
建築積算士とは、「建築生産過程における工事費の算定並びにこれに付帯する業務に関し、高度な専門知識及び技術を有する専門家」と定義されており、求められる技術としては「建築工事分野の数量算出・工事費算定」と規定されています。
1979年に(公社)日本建築積算協会の民間資格として誕生しましたが、1990年に建設省告示第74号により大臣認定資格として「建築積算資格者」に衣替えしました。その後、行政改革の一環として大臣認定制度は廃止され、民間資格「建築積算士」として現在にいたっています。
なお、3年ごとに資格更新があり、更新講習(eラーニング)の受講が更新要件となっています。
建築積算士の仕事内容
建築積算士の主な仕事は、設計の川上段階における工事費の概算数量算出・金額算定から実施設計完了後における工事費の精算数量算出・金額算定までとなります。
設計事務所や施工者(ゼネコンや専門工事会社)あるいは積算事務所において、コストマネジメントの基本情報としての工事費を算定します。特に、公共工事の発注者及び設計者側においては予定価格(入札における発注額の上限値)を適正に算定し、施工者側においては過不足のないシビアな事前原価を算定するなど、建築プロジェクトが適正に進められるために様々な関係者における経済的な側面を支える仕事を担います。
建築積算士の試験概要
建築積算士の試験は、建築コスト管理士と同様に「(公社)日本建築積算協会」が実施しており、試験内容は、以下の「求められる知識」をテキスト化した「新☆建築積算士ガイドブック」から出題されます。
- 生産プロセス
- 工事発注スキーム(入札、発注方式、契約方式他)
- 設計図書構成
- 工事費構成
- 積算業務内容
- 建築数量積算基準
- 内訳書標準書式
- 主要な市場価格
- データ分析と積算チェック
- 施工技術概要
- LCC・VE概要
- 環境配慮概要
建築積算士の受験資格は満17歳以上となっており、その他の要件はありませんので受験しやすい資格となっています。
試験は一次試験と二次試験で構成されており、一次試験は学科試験(4択式)、二次試験は積算実技試験と短文記述試験となっています。また、一次試験の合格者が後日二次試験を受験できる仕組みとなっています。
また、建築士、施工管理技士、建築積算士補、過去の一次試験合格者などについては、二次試験から受験することができます。
合格基準点は、正答率60%程度がおおよその目安となることが公表されています。
建築積算士の難易度
過去の建築積算士二次試験の合格率(資格取得者)は以下の通りとなっています。
| 試験年度 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 |
| 2024年 | 59.5% | 968人 | 576人 |
| 2023年 | 62.0% | 988人 | 613人 |
| 2022年 | 58.1% | 778人 | 452人 |
| 2021年 | 64.7% | 759人 | 491人 |
| 2020年 | 63.1% | 523人 | 330人 |
| 2019年 | 69.3% | 644人 | 446人 |
| 2018年 | 58.7% | 678人 | 398人 |
※公益社団法人日本建築積算協会による「建築積算士認定事業による試験実施結果」公表データから独自作成
建築積算士試験は、毎年の二次試験合格率がおおよそ60%前後となっています。一次試験についてはおおよそ60%半ばとなっていますので、一次・二次を通算する合格率は40%程度と推定できます。他の建築関係の資格のうち、たとえば「一級建築士」の合格率が約10%、「二級建築士」の合格率が約25%程度であることを考えると、やや難関ではあるものの、比較的合格率の高い資格といえるでしょう。また、出題範囲と合格基準点が明確で、ホームページに過去問も公開されていることから、受験勉強しやすい資格ともいえるでしょう。
建築積算士資格を取得するメリット
建築積算士の資格を取得することによって、次のようなメリットがあります。
- CM(コンストラクション・マネジメント)や建築設計などの業務プロポーザルにおいて、多くのプロジェクトにおいては技術者の資格要件あるいは評価点の対象資格となっている。
- 建築業界における就職や転職時に有利となる
- 上級資格にあたる建築コスト管理士を目指せる
- 仕事の幅が広がる
設計や施工において、積算は必須の業務です。積算のスキルを持つ人材は建設産業界において欠かせないため、建築積算士の資格を取得することによって、就職や転職時に有利となる可能性は高いと言えるでしょう。
また建築積算士の資格を取得すれば、建築コスト管理士を目指しやすくなります。建築積算士や建築コスト管理士を取得すれば、年収アップやキャリアアップなどにもつながるので、様々なメリットがあると言えるでしょう。
建築積算士補とは?
ここで、学生向けの資格である建築積算士補についても少し触れてみましょう。
建築プロジェクトにおいて経済性つまりコストは非常に重要な要素と認識されています。しかし、我が国の建築に関する学校教育においては、建築コストあるいは積算についての教育はほとんど行われてきませんでした。建築技術者として社会に出た大部分の新人は、建設行為には必ずお金がついて回るという至極当然な事実に直面し、悩むことになります。
(公社)日本建築積算協会は、2009年に大学、短大、高専、高校、専門学校、職業訓練校など様々な教育機関を対象に認定校制度を創設し、現在、約60校で「建築積算講座」を開設しています。同講座を修了し資格試験に合格して登録を行った学生は、「建築積算士補」の資格を取得することができます。
毎年3,000名程度の学生が講座を受講し、2,000名程度が建築積算士補を取得しています。これらの「コストについての基礎知識と意識を身につけた人材」が社会に巣立ち、建築産業界の様々な分野で活躍しているのです。
建築積算士補は、「建築生産過程における工事費の算定並びにこれに付帯する業務に関して、基礎的知識を有するもの」と定義されており、資格に求められる知識としては、「生産プロセス概要、工事発注スキーム概要、設計図書構成、工事費構成、積算業務・実務概要、LCC・VE概要」となっています。
建築積算士補は建築積算士の一次試験が免除され、建築積算士補を取得した学生が在学中に建築積算士試験に合格する例も増えており、就職活動に有効であったとの事例も聞かれるようです。
建築コスト管理士と建築積算士と違いとは
建築コスト管理士資格と建築積算士の主な違いは、以下のとおりです。
| 建築コスト管理士 | 建築積算士 | |
| 資格の定義 | ・企画・構想から維持・保全、廃棄にいたる建築のライフサイクル全般に渡って、コストマネジメント業務に関する高度な専門知識および技術を有する専門家。 | ・建築生産過程における工事費の算定並びにこれに付帯する業務に関し、高度な専門知識および技術を有する専門家。 |
| 求められる技術 | ・各フェーズに応じた工事費用、 その他費用の算定・コストプランニング・コストコントロール | ・建築工事分野の数量算出・建築工事分野の工事費算定 |
| 求められる知識 | ・コスト情報収集・分析・広範囲な市場価格・発注戦略・調達戦略・フィジビリティスタディ・概算技法、施工・技術・工期算定・LCC・VE及びFM・PM・CM概 要・環境配慮・建築関連法規・IT活用・原則として建築積算士に求めら れる知識を包含する | ・生産プロセス・工事発注スキーム・設計図書構成・工事費構成・積算業務内容・建築数量積算基準・内訳書標準書式・主要な市場価格、データ分析 と積算チェック・施工技術概要・LCC・VE概要・環境配慮概要 |
すでに説明した通り、建築コスト管理士は建築積算士の上位資格です。
このため建築積算士が「建築生産過程における工事費の算定並びにこれに付帯する業務」を行うのに対し、建築コスト管理士は建築積算士が算定したコスト情報をベースに、「企画・構想から維持・保全、廃棄にいたる建築のライフサイクル全般に渡ってのコストマネジメント業務」などの、よりレベルの高い業務を行うことが想定されています。
資格の取得を目指すべき人とは
建築関連の仕事に関わっている人の中には、自分が建築積算士や建築コスト管理士資格を取得すべきなのか知りたいという人も多いのではないでしょうか?
建築コスト管理士を目指すべき人
建築コスト管理士の資格取得を目指すべき人は、次のような人たちです。
- 発注者側のプロジェクト責任者や担当者
- 設計事務所のプロジェクト統括責任者あるいはコスト担当者
- 建設会社のコスト部門担当者
- 官公庁のコスト管理責任者
- 積算事務所のプロジェクト統括責任者
- 建築積算士を取得しておりキャリアアップを狙っている人
建築積算士を目指すべき人
建築積算士の資格取得を目指すべき人は、次のような人たちです。
- 設計事務所のコスト担当者
- 建設会社のコスト部門担当者あるいは工事部門現場管理担当者
- 積算事務所の担当者
- 官公庁のコスト管理関係者
建築コスト管理士と建築積算士の資格を取得して業務の幅を広げましょう!
建築コスト管理士は「建築のライフサイクル全般に渡ってのコストマネジメント業務を行う専門家」、そして建築積算士は「建築生産過程における工事費の算定などを行う専門家」です。
常に慢性的な人材不足に悩まされている建設産業界において、どちらも貴重な技術力を証明する資格であり、取得することによってキャリアアップや収入アップにもつながります。
今よりも業務の幅を広げたい、もしくはキャリアアップや転職を考えている人は、建築コスト管理士や建築積算士の資格取得を目指してみてはいかがでしょうか?
なお、(公社)日本建築積算協会のホームページに、資格に関する様々な情報とともに、企業別の資格者数に関する情報「資格者数調査票」が公開されています。どのような企業に何名の資格者がいるか、資格の有効性を確認する意味でもぜひご確認ください。