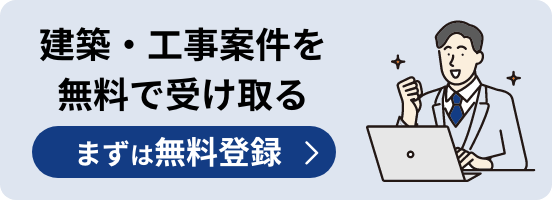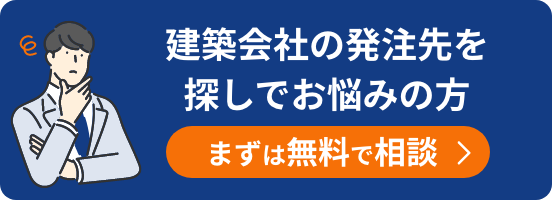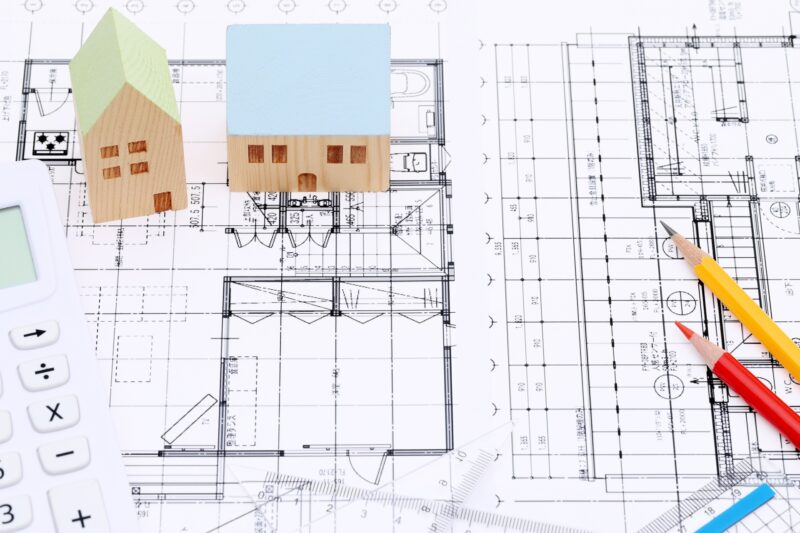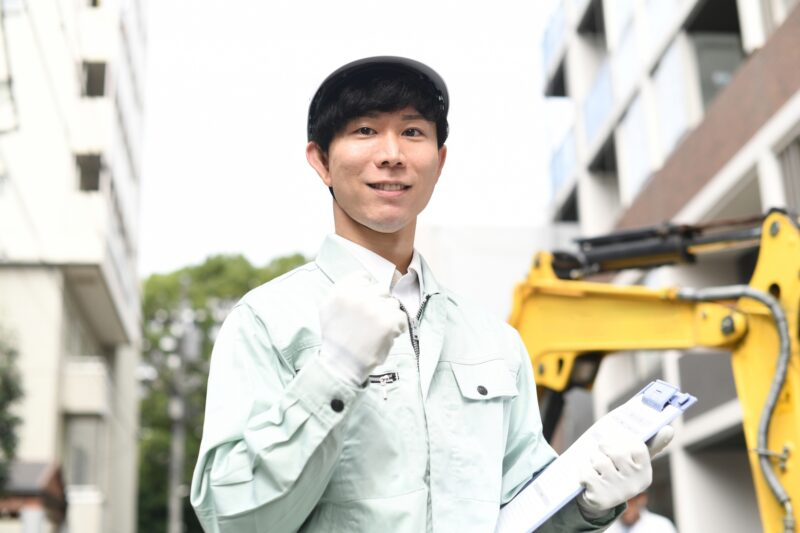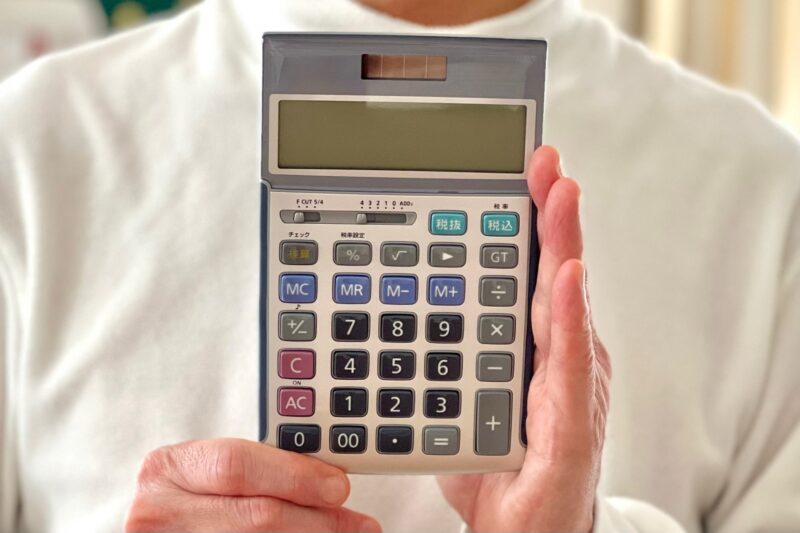下請取引において親事業者から不当な扱いを受けないよう、下請企業を守ることを目的とする「下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、基本的に建設工事に係る下請負(建設工事の再委託)には適用されません。しかし、取引が製造委託あるいは情報成果物作成委託に該当する場合には適用されるケースもあります。
この記事では下請法の主な内容と建設工事に適用される事例、そして基本的に建設工事の下請取引に適用される建設業法について紹介していきます。
下請法とは?
下請法(正式名:下請代金支払遅延等防止法)とは、大手企業が小規模企業や個人事業主に対して行う、不当な取引行為を禁止する法律です。具体的には、商品やサービスの対価を不当に減額したり、理由のない返品を行ったり、支払いを遅延させたりすることを禁じています。
下請法の目的
下請法の目的について、条文の第1条にはこのように書かれています。
| 第一条 この法律は、下請代金の支払遅延等を防止することによつて、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。 |
下請法の直接的な目的は「下請代金の支払遅延等」の防止によって「下請け事業者の権益を守る」ことです。しかし究極的には「国民経済の健全な発展」を目的としています。
適用される取引
下請法の対象となる取引は、以下の4種類です。
- 製造委託
製造委託とは製品や部品などの製造を他社に委託する取引です。例えば、自動車メーカーが部品製造を下請け事業者に依頼するケースなどがこれに該当します。
- 修理委託
修理委託とは、機械や設備の修理や保守を他社に委託する取引です。これには製造ラインの機械のメンテナンスやビルの設備修理などが含まれます。
- 情報成果物作成委託
情報成果物作成委託とは、ソフトウェア開発、ウェブコンテンツ作成、データ解析など、情報を生成したり編集したりする業務を他社に委託する取引です。IT開発などを外部のエンジニアや企業に依頼するケースがこれに該当するでしょう。
- 役務提供委託
役務提供委託とは、特定のサービスや機能を他社に委託する取引です。例えば、製品の運送や、カスタマーサポート、決済処理、データ入力などの業務が含まれます。
対象となる事業者
下請法の適用対象となるのは「親事業者(元請け事業者)」です。親事業者の定義については下請法第7条で細かく指定されています。
①製造委託、修理委託、政令で定める(委託内容の)情報成果物作成委託と役務提供委託の場合
・資本金3億円を超える法人で、個人や資本金3億円以下の法人に委託する者
・資本金1,000万円を超える法人で、個人や資本金1,000万円以下の法人に委託する者
②情報成果物作成委託と役務提供委託の場合(①に該当しないもの)
・資本金5,000万円を超える法人で、個人や資本金5,000万円以下の法人に委托する者
・資本金1,000万円を超える法人で、個人や資本金1,000万円以下の法人に委託する者
おおまかには、個人事業主や自社より資本金の小さい企業に業務委託する場合は「親事業者」になる(下請法の適用対象になる)と考えておけば良いでしょう。
下請法による「義務」と「禁止行為」
下請法の重要なポイントとなるのは「4つの義務」と「11の禁止行為」です。それぞれについてわかりやすく説明していきます。
4つの義務
親事業者には、以下の4つの義務が課されます。
①下請代金の支払期日を定める義務
下請代金の支払期日は、下請事業者の業務完了から60日以内で設定します。ただし下請法第2条の二には「できる限り短い期間内において定められなければならない」とあるため、支払いは可能な限り早いタイミングで行う必要があります。
②発注書面を交付する義務
取引の内容を明確にするため、親事業者は下請事業者に「給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面」を提供します。紙媒体のほか、デジタル媒体で交付する(メールで受信させる)ことも可能です。
③支払が遅延した場合に利息を支払う義務
あらかじめ設定した支払期日までに下請代金が支払われなかった場合、親事業者は下請事業者に年利14.6%の遅延利息を支払わなくてはなりません。利息計算の起点となるのは、受注した物品等を受領した日から数えて60日を経過した日からです。
④取引に関する書類を作成・保存する義務
親事業者は、下請事業者に交付する紙媒体もしくはデジタル媒体の書面を作成し、それを2年間保管しなければなりません。
11の禁止行為
親事業者には、以下の11種類の行為が禁止されます。
①受領拒否の禁止
受領拒否とは下請事業者の納品を拒むことです。請負事業者に責任がないのにかかわらず受領拒否をすることは許されません。
②下請代金の支払遅延の禁止
契約の目的物(物品など)が納品された場合、あらかじめ設定した日(納品から60日以内)までに下請代金を支払わなくてはなりません。
③下請代金の減額の禁止
下請事業者に責任がないのに、発注時に決めた下請代金を発注後に減額することは許されません。これは下請事業者との「合意」がある場合も同様です。
④返品の禁止
親事業者が契約の目的物(物品など)を受領した場合、それが下請事業者に責任がある不良品などの場合をのぞき、返品することはできません。また不良品などを返品する場合は速やかに(6か月以内に)行なう必要があります。
⑤買いたたきの禁止
下請代金を決める際に、同等の契約内容で通常支払われる対価(一般的な相場)よりも著しく低い金額で「買いたたく」ことは許されません。なお、下請代金にコスト上昇を反映しない場合も「買いたたき」と見なされることがあります。
⑥購入・利用強制の禁止
親事業者は、正当な理由がないにもかかわらず下請事業者に特定の製品・原材料を購入するように強制したり、サービスを強制的に利用させることはできません。
⑦報復措置の禁止
親事業者が下請法に違反し、そのことを下請事業者が公正取引委員会や中小企業庁に報告した場合、報復として取引の縮小や停止など下請事業者にとって不利な扱いをすることは許されません。
⑧有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
下請事業者に特定の部品や原材料などを購入させている場合、下請事業者に責任がないにもかかわらず、その代金を下請代金よりも早いタイミングで支払わせたり下請代金から控除することはできません。
⑨割引困難な手形の交付の禁止
下請代金を手形で支払う場合、それを一般の金融機関で割引困難な手形として交付することは許されません。
⑩不当な経済上の利益の提供要請の禁止
親事業者が下請事業者に、金品やサービスといった「経済上の利益」を不当に要求することはできません。
⑪不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
下請事業者に責任がないにもかかわらず発注を取り消したり、発注内容を不当に変更したりすることはできません。また目的物の受領後に、(下請事業者に責任がないのに)やり直しをさせることもできません。
下請法に違反したら?
公正取引委員会は、親事業者や下請事業者に取引について報告をさせたり、事務所・事業所に立入検査をすることができます。
親事業者が下請法に違反した場合は、公正取引委員会が勧告や指導により、親事業者の違反行為をやめさせたり、下請代金の減額分を下請事業者に返還させたりします。また、勧告が行われた場合は企業名などが公表されます。
特に、4つの義務のうち「②書面の交付」と「④書面の保管」に違反した場合、親事業者には公正取引委員会から罰則(50万円以下の罰金)が科されます。
建設工事で下請法が適用されるケース
原則として、建設工事に係る下請負には下請法が適用されません。しかし、以下のような製造委託および情報成果物作成委託に該当する取引に限り下請法が適用される場合があります。(公正取引委員会Q&A)
① 建設業者が業として建設資材を販売しており、その建設資材の製造を他の事業者に委託する場合(製造委託・・・類型1)
② 建設業者が請負った建設工事に使用する建設資材の製造(自家使用する物品を業として製造している)を他の事業者に委託する場合(製造委託・・・類型4)
③ 建設業者が請負った建築物等の設計又は工事図面の作成を他の事業者に委託する場合(情報成果物作成委託・・・類型2)
④ 建売住宅を販売する建設業者が、建築物の設計図等の作成を他の事業者に委託する場合(情報成果物作成委託・・・類型1)
建設業法における下請事業者への配慮
建設業法は、建設業の許可、建設工事の請負契約、紛争処理、施工技術の確保、建設業者の経営に関する事項の審査、建設業団体、建設業の監督などに関する広範囲な法律となっています。そのなかで、下請事業者が不利益を被らないような配慮がなされています。
建設工事の下請契約に関しては、一部「下請法」に該当する取引を除き、原則として「建設業法」が適用されることになります。
建設業法「第三章・建設工事の請負契約」は、発注者と受注者(元請負人である建設業者)間の工事請負契約に関する内容ですが、元請負人と下請負人との間の下請契約にも適用されるものと考えられます。
特に「第二節・元請人の義務」は、「第一節・通則」第18条の「請負契約の当事者が対等な立場における合意に基づき公正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行する」という請負契約の原則を下請契約で実現するための具体的な規定となっています。
以下に代表的な内容を紹介します。
下請契約の締結の制限:第16条
特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請負った建設工事を施工するための下請契約については、政令で定める金額※1(複数の契約の場合は総額)以上となる契約を締結できません。
※1(2025年2月1日改正 建設業法)
下請契約 5,000万円(建築一式工事 8,000万円)
元請負人の義務:第三章 建設工事の請負契約の第二節 (第24条)
① 下請負人の意見の聴取
元請負人は、建設工事を施工するため必要な工程の細目、作業方法その他を定める場合は、あらかじめ下請負人の意見を聞かなければなりません。
② 下請代金の支払
元請人が請負代金の支払を受けたときは、該当する建設工事の下請負人に対して、支払を受けた日から1月以内でかつできる限り短い期間で支払わなければなりません。
また、労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければなりません。
なお、元請人が前払い金の支払を受けたときは、資材の購入、労働者の募集など工事の着手に必要な費用を支払うよう適切な配慮をしなければなりません。
③ 検査及び引き渡し
元請負人は、下請負人から請負った工事の完成通知を受けたときは、20日以内でかつできるだけ短い期間内に完成確認の検査をしなければなりません。
また、下請契約において引渡し日の特約がない場合、完成確認の検査後に下請負人が申し出たときは、直ちに目的物の引き渡しを受けなければなりません。
④ 不利益取扱いの禁止
元請負人は、請負契約における「不当に低い請負代金の禁止(第19条3)」「不当な使用資材等の購入強制の禁止(第19条4)」「下請代金の支払時期や方法など(第24条3・6)」などの禁止規定に違反する行為があるとして、下請負人が国土交通大臣や公正取引委員会その他に事実を通報したことを理由に、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはなりません。
⑤ 特定建設業者の下請代金の支払期日等
特定建設業者が注文主となった下請契約においては、下請代金の支払日を、下請負人から工事完成引渡しの申し出があった日から50日以前のできる限り短い期間内に定めなければなりません。支払期日が50日を超えて定められた場合は、50日を経過する日が支払期日とみなされます。(前項②のように注文主から支払を受けていない状況においても、特定建設業者の場合は支払期日が制約されています。)
また、一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付できません。
支払期日までに下請代金を支払わなかった場合は、50日を経過した日から支払をするまでの期間について延滞利息(国土交通省令の率)を支払わなければなりません。
ただし、下請負人が特定建設業者あるいは政令で定める一定額以上の資本金※2の法人の場合は、この条文は適用されません。
※2 資本金4,000万円以上
⑥ 下請負人に対する特定建設業者の指導等
注文主から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請負人が建設業法の規定又は工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定等に違反しないよう、下請負人の指導に努めなければなりません。
特定建設業者が法令等の違反を是正指導し、下請負人が是正しなかった場合は、国土交通大臣あるいは都道府県知事にその旨を通報しなければなりません。
⑦ 施工体制台帳及び施工体系図の作成等
注文主から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、建設工事の適正な施工を確保するため、政令で定める請負代金額※1以上の契約をした場合、各下請負人の商号その他国土交通省令で定める事項を記載した「施工体制台帳」を作成し、工事現場に備えおかなくてはなりません。
下請負人は、請け負った建設工事を他に請け負わせた(二次下請)場合は、下請負人の商号その他国土交通省令で定める事項を特定建設業者に通知しなければなりません。
発注者から請求があった場合は、施工体制台帳を閲覧に供しなければなりません。
また、下請負人の施工の分担関係を表示した「施工体系図」を作成し、工事現場の見やすい場所に掲げなければなりません。
※1(2025年2月1日改正 建設業法)
下請契約 5,000万円(建築一式工事 8,000万円)
建設業法違反に対する措置
① 国土交通大臣又は都道府県知事は、上記の規定に違反し、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」第19条(不公正な取引方法の禁止)に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し適当な措置をとるよう求めることができます。
また、下請負人が中小企業者※3の場合は、中小企業庁長官に通知しなければなりません。
※3 資本金3億円以下、従業員300人以下のいずれかに該当する者
② 中小企業庁長官は、中小企業者である下請負人の利益を保護する必要を認めたときは、元請負人と下請負人に対して報告・立ち入り、書類等の検査を行うことができます。
中小企業庁長官は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」第19条(不公正な取引方法の禁止)に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し適当な措置をとるよう求めることができます。また、国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければなりません。
つまり、下請負人が中小企業者の場合は、国土交通省と中小企業庁の双方から公正取引委員会に措置請求がなされることになります。
下請法と建設業法を理解して建設プロジェクトを円滑に進めましょう
下請法および建設業法は、健全な商取引を保証するための重要な法律です。特に、建設業法は建設工事に関する下請契約の双務性についてきめ細かく規定しています。
下請法および建設業法の遵守は公平で健全なビジネス環境を維持し、建設プロジェクトを円滑に進めるうえで欠かせません。工事に関わるすべての事業者は、ぜひこの記事を参考にしながら、下請法と建設業法についてしっかり理解するようにしましょう。いてしっかり理解するようにしましょう。