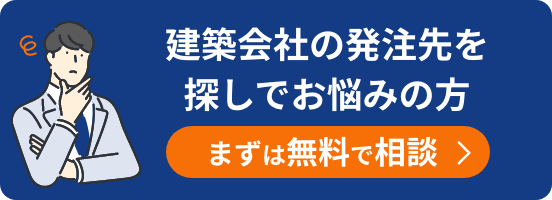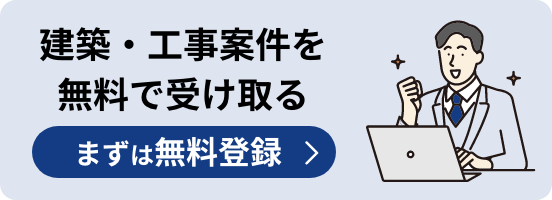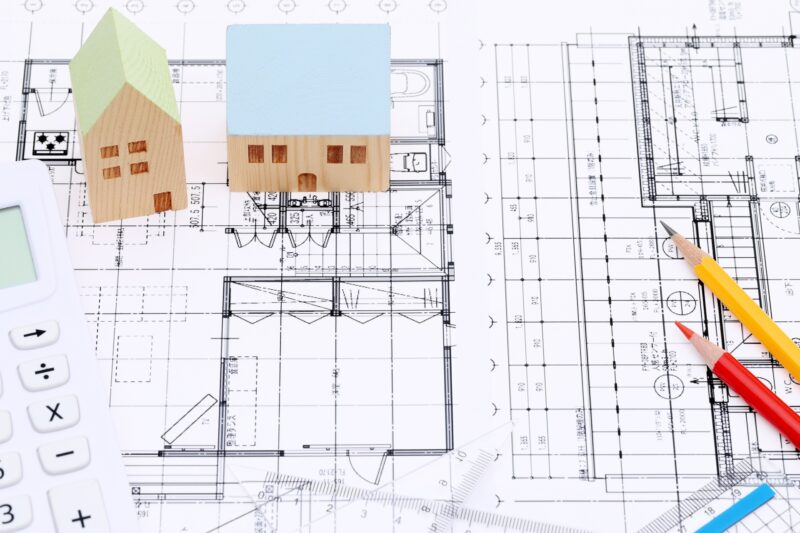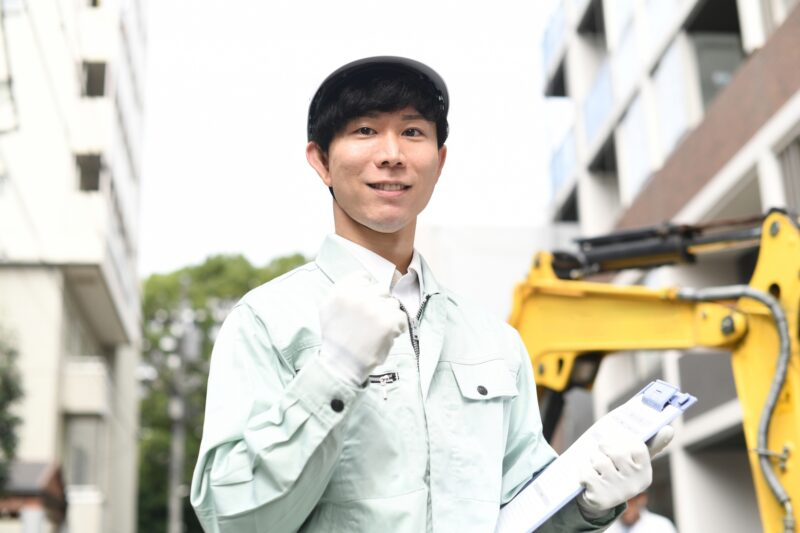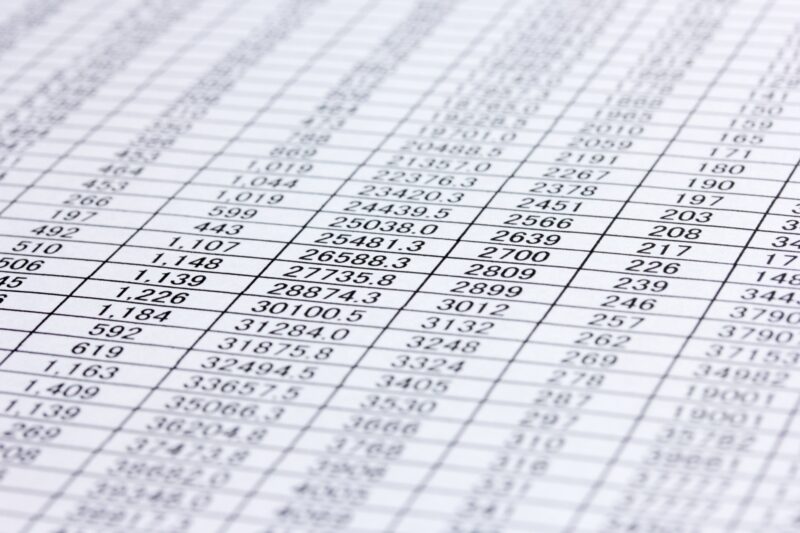完成工事高とは、完成した工事の売上高や収益のことを指します。本記事では、完成工事高の概要や他の勘定項目との違い、類似勘定項目との関係性や、完成工事高の計上基準・用途について解説します。
民間事業者に特化した建築発注プラットフォーム「タチドコロ」は、様々な建築物に対応できる設計事務所や建設会社を探す事が可能。条件に合った複数の会社と同時に比較・交渉ができるだけでなく、WEB上でのマッチングに加えて、専門のコンシェルジュが受発注業務をサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
完成工事高の意味と役割
完成工事高とは、建設工事が完成した際の売上高や収益のことです。一般的な企業では完成工事高ではなく「売上高」という表現を使いますが、内容的な違いはほとんどありません。
完成工事高と他の勘定科目の違い
完成工事高と他の勘定科目との違いや関係について説明していきます。
完成工事原価
完成工事原価とは、完成工事高の「原価」を指す勘定科目です。一般的な企業や業界においては「製造原価」とも言われています。
完成工事原価は「材料費・外注費・労務費・経費」で構成されており、完成工事高から完成工事原価を引いた金額が企業の純利益となります。
施工高(出来高)
施工高(出来高)とは、受注した工事のうち完成した部分の金額です。
後述する完成工事高の計上基準において「工事進行基準」を採用する場合、施工高は当期の完成工事高と同じになります。
一方で「工事完成基準」を採用している場合、当期に工事が完成した場合にのみ施工高と完成工事高が同じとなります。
手持ち工事高
手持ち工事高とは、受注高から施工高を引いた金額のことを指しており、将来における完成工事高を意味します。
次期繰越高
次期繰越高とは、受注している請負契約のうち未着工部分の金額のことであり「次期」の完成工事高を指します。
次期繰越高が多ければ多いほど「来期の完成工事高が多くなる」ので、企業として収入が安定している基準となります。
完成工事未収入金
完成工事未収入金とは、完成工事高として計上している金額の中で「相手から回収することができていない金額」を指します。
もっとも完成工事未収入金として計上するのは「未回収の金額のうち決算期から1年以内に回収することができる予定のもの」のみであり、回収するのが1年以上かかりそうなものは投資もしくはその他の資産として計上しなければなりません。
一般的な企業や業界においては「売掛金」と表記されます。
工事未払金
工事未払金とは、工事のために購入した資材の金額や下請けに支払わなければならない外注金額の「未払金」のことです。
一般的な企業や業界においては「買掛金」と表記されます。
未成工事支出金
未成工事支出金とは「完成していない工事の原価」のことです。
企業の貸借対照表においては流動資産として記載され、工事が完成することによって「完成工事原価」へ移ります。
未成工事受入金
未成工事受入金とは「工事が完成してないうちに相手から受け取った金額」のことです。
貸借対照表においては「流動負債」として記載され、工事が完成した後に完成工事高へ振り分けられます。
建設業でさまざまな勘定科目が使われる理由
建設業界では特殊な名称の勘定科目が多く使われます。
これは建設業界において「複数年にわたって工事が継続して行われる」という特殊な事情があるためです。
一般的な企業や業界においては、金銭の発生する取引はその場で行われるか、長くとも1年以内に終了します。しかし建設工事は何年にもわたって行われることがほとんどであり、一般的な会計のやり方や勘定科目を使っていると不都合が生じかねません。
こうした建設業界独特の問題を解決するために導入されたのが、建設業界独自の特殊な会計制度や勘定科目の表記の仕方なのです。
完成工事高の計上基準
完成工事高には2つの種類の計上基準があります。
1.工事完成基準
工事完成基準とは、請負工事の売上や原価を収益や費用に計上するタイミングを「工事の完成・引渡しの日」にするという考え方です。
数年間にわたって行われる大規模な工事であったとしても、工事完成基準を採用していれば完成工事高の計上が1回で終わるので、会計上の手続きや処理がシンプルかつ手間がかからないという特徴があります。
ただし工事が完成するまでは一切の売り上げを会計上で計上することができず、支出だけを未成工事支出金として計上しなければなりません。
2.工事進行基準
工事進行基準とは、工事の完成や建物の引き渡しによって収益や費用を計上するのではなく「工事の進行している割合などに応じて収益や費用を計上する」という考え方です。
企業の税務的には、なるべく遅く収益を計上する方が有利になるため、工事進行基準を企業自ら選択することは多くありません。
ただし、一時的に決算書の見栄えをよくしたいという理由から、売り上げを前倒しして形状できる工事進行基準を採用する企業も存在しました。
3.完成工事高計上基準の現状規定
国際会計基準では工事進行基準のみで、工事完成基準は認められていません。
我が国においては、2007年に公表された「企業会計基準第15号」によって、2009年4月以降は以下の3点について確実性が認められる工事については全て工事進行基準が適用されることになりました。
- 工事収益総額
- 工事原価総額
- 決算日における工事進捗度(累計発生原価/見積工事原価総額)
なお、請負代金額の大小にかかわらず、工期のごく短い工事は工事完成基準を適用します。ただしごく短い工期の具体的な数値は示されていません。
会計基準の改正に歩調を合わせる形で、税法上の完成工事高計上基準も改正されました。工事進行基準が強制される工事の要件は以下のようになりました。
- 工期は1年超(以前は2年超)
- 請負代金額は10億円以上(以前は50億円以上)
これ以外の工事に関しては、継続して適用することを条件に、工事進行基準と工事完成基準の選択が可能となっています。
完成工事高の活用用途
完成工事高の活用用途は、会計上の単なる勘定科目だけではありません。ここでは、知っておきたい完成工事高の2つの活用用途についてご紹介します。
経営事項審査
完成工事高は、公共工事を受注するにあたって必要不可欠な建設業の評価基準である「経営事項審査」の審査項目となっています。
経営事項審査においては「総合評定値(P)」と呼ばれる点数が評価の基準であり、その点数は次の4つの要素によって定まります。
- 経営規模(X)
- 経営状況(Y)
- 技術力(Z)
- その他の審査項目(W)
上記4つのうち経営規模(X)は2つに別れており、そのうちの1つが許可業種別の完成工事高です。経営事項審査では受注したい工事の業種によって、請負金額100万円以上の完成工事高を許可業種別に報告する必要があります。
完成工事高は、総合評定値(P)の1/4を占めており、数値が高ければ高いほど、評価も高くなります。ただし、評価を高めるためにむやみやたらと工事の受注量を増やしたからと言って、完成工事高が増えるわけではありません。
企業としてきちんと利益が得られるように、工事を適切に受注しているかどうかというのも重要なポイントとなります。
統計調査
完成工事高は、建設業界における統計調査でも利用されています。
建設工事の統計調査は、国が建設工事や建設業界の実態を明らかにするために行っており、次の3つの種類があります。
- 建設工事受注動態統計調査
- 建設工事施工統計調査
- 建設統合統計
完成工事高の意味についてしっかりと理解しておこう!
完成工事高は経営事項審査において重要な審査項目です。
公共工事を受注したいと考えている企業は、経営事項審査を有利にするためにも、まずは完成工事高の内容をしっかり理解して「受注する工事の内容」や「計上基準の方法」などの工夫に取り組んでみてください。
民間事業者に特化した建築発注プラットフォーム「タチドコロ」は、様々な建築物に対応できる設計事務所や建設会社を探す事が可能。条件に合った複数の会社と同時に比較・交渉ができるだけでなく、WEB上でのマッチングに加えて、専門のコンシェルジュが受発注業務をサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。